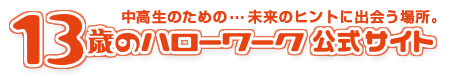HOME > もっと教えて!フォーラム > 生命を扱う「医療・福祉」の仕事 > 回答・コメントする(No.10785)
もっと教えて!フォーラム
回答・コメントする(No.10785)
-
いつも、子どもたちの疑問にお答えいただき誠にありがとうございます。
13hw編集部より、ご回答くださる際のポリシーに関するお願いです。
-
回答は、基本的には、その職業の方(または経験者、相応の知識を有する方など)にお願いしております。
しかしながら、なかなか回答のつかない質問もあります。
投稿されてから2週間経っても回答がつかない質問に関しましては、職業などに関係なく、ご回答のご協力をお願いしたいと考えております。 -
白書の皆様におかれましては、貴重な時間を割き、子どもたちの質問に丁寧にお答えくださったり、叱咤激励してくださって誠に感謝しております。
このようなお願いをするのは大変恐縮なのですが、勇気を出してこのサイトに質問を投稿してくれた子ども達に、よりよい情報を提供したいと考える当サイトの運営ポリシーをご理解・ご了承いただけますと幸いです。
 医者を目指しているのですが、血などが苦手なのでとても不安です。
医者を目指しているのですが、血などが苦手なのでとても不安です。
[Q] 私はこの春、高校2年生になりました。
中学3年生あたりから医者になる夢を持ち始め、勉強をして県内トップに近い高校にも入れました。
そこで、一番の不安は、血などが苦手なことです。
魚をさばいたり、擦り傷程度の血を見るのは平気なのですが、テレビなどで見る大怪我などは、見ていてとても恐怖を感じます。
また、骨折や突き指、アキレス腱を切るなど、出血をすることの無い怪我も苦手で、保健の授業などでは、聞いているだけで指が痛くなったり気分が悪くなったりします。
勉強をしていても、そのことが頭にあって「無理かもしれない」と思ってしまいます。
大学で勉強・実習をしている内に慣れるものなのでしょうか?

こんにちは、ななやのさん。
中学3年の頃からの夢を、今も持ち続けているのですね。
いいですね。
医者という仕事は、
一般的に「頭が良くないとなれない」とか、「なるのは大変」
と言われていますが、ななやのさんは、どうして医者になりたいのですか。
私の勝手な感想ですが、
ななやのさんなら、「慣れる」と思いますよ。
中学3年生の頃から思い続けていて、
今でも「医者になりたい」と思っているのですから…
そのように思い続ける「力」って、とても大事だと思います。
どんな仕事も大変なことはあるし、初めのうちは慣れないものです。
でも、医者であれば、
「この人の命を救いたい」とか「少しでも回復させたい」
という思いがあれば、慣れてくるのではないでしょうか。
医者の役割や使命感を忘れずに、
目標とする大学を目指して頑張って下さいね。
血液を見なくても済む診療科もありますしね…

早くから目標を持っていていいですね。
さて、お答えですが・・・慣れます。
私は外傷を扱うという仕事柄よく大怪我で凄惨な場面に遭遇します。学生時代はただただ気持ち悪くて仕方がありませんでした。
でもまあ、外傷を診ない科に進めばほとんどみないんですけどね!

はじめまして、ななやのさん。内科医のマリオンと申します。
先に、はっきりした意見が並びました。特に、あやころりんさんの御意見は、医療を受ける側の本音だと、私は思いました。
ななやのさんに逆質問してみよう。
あなたはなぜ、魚をさばく時に出る血は平気なのでしょうか?
一方、私は料理ベタで、調理中ときどき包丁で指を切ってしまいます。先日なかなか血が止まらなかった時、主観的には「このまま死んだらどうしよう」と少しだけ悲しくなりました(少しだけですよ)。客観的に医師の目でみると、死ぬわけがない程度の出血にも関わらず。
一方、自宅で家族の誰かが血を流しているのを見ると「大変!」と一瞬慌てます。そして2秒後ぐらいに医者に変身して、「圧迫止血」とか言い出します。
ところが、職場(病院)で内科医に変身後は、患者さんが出血していても慌てない。
この違いは何でしょうか?
解剖学者 養老孟司先生のお話の受け売りですが、身体には3種類あるという解釈があります。
①1人称(「私」)の身体
②2人称(親密な関係の人、例えば家族・恋人)の身体
③3人称(赤の他人)の身体
血の赤さは、身体損傷を示す危険信号の色。それを見て恐怖反応が出るのは、程度の差こそあれ、まあ普通と言えましょう。
しかし、3人称の身体から出る「血」というのは、1人称と2人称の身体危機ではありません。脳の中に知識を植え付けることで恐怖反応を抑えることができます。そして、怖がるよりも先に、医療として何をするか考えるようになります。
これが医学教育の成果です。最初は教科書で身体の仕組みを学んで、人体解剖して・・・脳に異なる思考パターンを仕込むのは結構時間がかかります。
ある建築評論家の言葉を引用して、あなたに贈ります。
「プロフェッショナルになるということは、一般人と異なる認識を獲得するプロセスなのだ」
(五十嵐 太郎 著 「美しい都市・醜い都市 現代景観論」より)

「向いてないからあきらめなさい」と言われてすぐにあきらめ切れるなら、所詮それだけの思いです。不安がるだけ労力の無駄ですから早くあきらめて他の道を探しましょう。ただ今のままのあなたでは、たとえ他の道を選んでも、「向いてるでしょうか?」「やれるでしょうか?」と結局は別の理由で「不安」になるでしょうね。
どんな仕事も慣れるまでは苦労もしますし辛いこともあります。ストレスゼロで最初からリタイアまで勤め上げられる仕事など、医師に限らずどこにもありません。苦労はしてもその仕事で世の中の役に立ちたいという「覚悟」が持てないから「不安」に振り回されるのです。怠慢の正当化を「不安」と言い換えて自分を騙していないか、内省してみてはいかがですか?

医療関係者ではありません。
門外漢からの回答で恐縮ですが、数度の外科手術を「患者として」受けた者として、思ったことを忌憚なく述べさせていただきます。
いま自分を治療してくれている医者の心中なんて、その時、治療されてるまっ最中の患者にとって、「どうでもいい」ことです。
お医者さん、特に外科医でしたら、傷に粛々と対峙してほしい、最良の処置を施してほしい、その知識と技術を持っていてほしい、と願うだけです。
つまり、ななやのさんが血が苦手だろうが、平気だろうが、患者をはじめ周囲には「関係ない」です。
安全に、苦痛少なく、ちゃんと、誠実に対応してほしいだけです。
「そうしてくれない」可能性が有るのなら、わざわざそういう人に医者になってもらわなくてもいいなぁ、と思ってしまいます。
そりゃ、ある程度多く血や傷に接していたら「慣れ」もするんじゃないですか?
怪我や血が得意で大好き!なんて人もいないと思います。
だってそれらは、「非日常」ですから。
その「非日常」にあえて踏み込んでいくのが医療現場の人たちですよね?
心配で心配で、それで二の足を踏む程度なら、やめといた方が良いんじゃないでしょうか。
怪我や血に関わるたびに、気分が悪くなって作業に影響が出たり、対応にマイナスになられたりする医学生なんてのは、同僚や指導医からしても、正直、メンドくさいだろうし…
ほんとに慣れるのかどうかは、医療関係の方のコメントにお任せします。
慣れないまでも、自分の気持ちはヨコに置いておいて、怪我や血に、ちゃんと対応しようとすることができるか、できないか、って事だけではないですか?
自分の心、そこにまで不安を覚えてしまうなら、速攻、進路変更をしたほうが良いと思います。
ななやのさんが「医者になろう」と思った動機と、「イヤかも」の気持ちを天秤にかけて、どちらが重いか、ですから。
ものすごく好意的に考えれば、そういう「痛み・苦しみに敏感な人」なら、傷つき苦しむ患者の立場に親身になって、我が身に対するように接し、良かれと思って最大限の対応をしてくれるお医者になるのでは?! というのもあります。
私の兄弟は医者なのですが、様々な研修過程で、自分の向き・不向き、得意・不得意、は、確実にわかったようです。
自分の得意な、そしてやりたい分野の生かせる病院で、いま仕事中です。
ちなみに私は歌手です。ステージに立つのは少なからず緊張しますし心身の負担も大きく、キツいのですが、それでも人様より歌うことが得意であり、人にそれを求められるので歌集を続けています。
やりたくない事を他人は強制しません。
ななやのさんが「医者になろう」、という気持ちが、どれほどのものなのか、また、それに対して「どれだけ努力できるか」っていうこと、それに尽きるお話なのではないでしょうか?