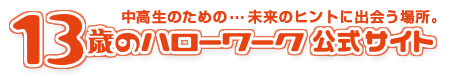HOME > もっと教えて!フォーラム > その他仕事・職業に役立つコト > 回答・コメントする(No.11952)
もっと教えて!フォーラム
回答・コメントする(No.11952)
-
いつも、子どもたちの疑問にお答えいただき誠にありがとうございます。
13hw編集部より、ご回答くださる際のポリシーに関するお願いです。
-
回答は、基本的には、その職業の方(または経験者、相応の知識を有する方など)にお願いしております。
しかしながら、なかなか回答のつかない質問もあります。
投稿されてから2週間経っても回答がつかない質問に関しましては、職業などに関係なく、ご回答のご協力をお願いしたいと考えております。 -
白書の皆様におかれましては、貴重な時間を割き、子どもたちの質問に丁寧にお答えくださったり、叱咤激励してくださって誠に感謝しております。
このようなお願いをするのは大変恐縮なのですが、勇気を出してこのサイトに質問を投稿してくれた子ども達に、よりよい情報を提供したいと考える当サイトの運営ポリシーをご理解・ご了承いただけますと幸いです。
 被災地復興・街づくりなどについて学ぶにはどのような大学が良いのでしょうか?
被災地復興・街づくりなどについて学ぶにはどのような大学が良いのでしょうか?
[Q] 被災地の街づくりをしたいと考えていますが、どのような大学に行けばいいのかが決まっていないのでよろしくお願いします。

こんにちは。被災地の役に立つ学びをしたいというあなたの思いはとても大切で、ぜひそれを育ててほしいと、私は強く願います。マスコミなどで報道されるのはほんの一部ですが、被災地で動いている街づくりに関するプロジェクトの大半は、大学などの研究機関がサポートしています。
とはいっても、何を学べば役に立つのか分からない、と言うのも正直なところだと思います。ごく簡単に、ヒントになりそうなことをコメントしますので、よかったら参考にしてください。
1.こんな学問を学べばこんなことに役立つかもしれない、という例を、実に大ざっぱに考えてみましょう。変に難しく考えないことが大切です。
(1)経済に関すること…仕事がなければ人は生活できません。何をするにもお金がないと動かないのも事実です。身近なところでは、商店街をどうやって元に戻しましょう。こういうことは、経済学/政治に関する学問の出番です。
(2)災害を防ぐ仕組み…津波対策は何がいいか(防波堤or土地かさ上げなどなど)。避難の仕組みの整備は? 地震/津波に強い建物は? 被害を少しでも減らせる街の構造は? こういったことを学ぶこともできます。大半は理系です。
(3)人に関すること…いわゆる心のケアはもちろんですが、いわゆる「仮設孤独死」をどう防ぐか、とか、もう一度近所付き合いを復活させるには? といったメンタル面での復興を支える学問もあります。心理学・社会学などなど。
(4)その他…場所によっては、放射能の汚染除去なども必要でしょう。また、所有者がいなくなった土地の扱いなど、専門知識が求められる仕事は山ほどあります。
2.街づくりというのは、一つの学問だけで完結するものではなくて、数多くの学問分野が連携して、少しずつ進んでいきます。あなたがそのすべてに関わるのは、行政機関のトップでもならない限り無理ですから、まずは自分にとって少しでも関心があることを中心にして、こんな風に街づくりに関わっていきたいという姿を思い描いてください。
3.さて、実際のお仕事では、学問として学んだとおりには物事が動かないというのは、当然のことです。これは震災復興だろうがサラリーマン稼業だろうが同じです。特に、震災復興としての街づくりは、関係者の利害関係が直接ぶつかり合うので、理屈だけでは何も動かない。
ここで、だから何も学ばなくても大丈夫、というのは短絡的な考えでしょう。これは最近よくいわれる「日本ヤンキー化」と大差ない。
多くのプロジェクトで研究者がアドバイザーとして参加しているのには理由があります。それはおよそ:
(A)議論の出発点を提示すること。「どこから手をつけていいか分からない」から抜け出すことと言い換えてもいいでしょう。
(B)参加者(地元の方々)に何かを判断してもらうための資料を示すこと
(C)事業が効率的に運用できるよう、お手伝いすること
(D)この次の災害に少しでも役立つように、今を記録すること/一般化すること
の4点で説明できるでしょう。
もちろん、学問だけでは限界があって、実際にあなたが街づくりの仕事につけば失敗や挫折は数多く経験するはずです。それでもあなたが学んだことは、どこかで活かされるでしょう。だって、必要なんですから。
4.私の母校の大学は、先の阪神淡路大震災で大きな被害を受けました。私の後輩も2人世を去りました。阪神間の大学は震災後ずっと、今でもあの地震で何が起こったのかを追いかけ続けています(あまり表には出ませんが)。
今回の東北の震災で、現地に関西地区の大学のスタッフがけっこう多いのは、こうした経緯があります。阪神の地震では上手くいかなかった多くの事柄を、東北では少しでも改善したいという願いがあります。
災害からの復興には10年単位の長い時間がかかります。被災地の皆さんの熱意は何よりも大切ですが、それらを支える専門家の役割も重要です。その重みをしっかりと受け止めて仕事をこなせるためにも、よく学んでいただきたい。私はそう思います。

私の文章は長いかもしれませんが、どうやったら、貴方の悟りの段階を上げてやれるかと考えて書いています。
被災地復興は、東北地方から関東地方までの人たちでは熱い課題としてとりあげられていますが、
西のほうではどのように考えられているのか疑問です。
関西などのオバちゃんあたりが、復興税にケチをつけているとしたら、西の方からは、
「被災地復興にかかる予算は日本の中の重石」だと思ってる場合だってあります。
是非、西の方が復興についてどのように考えているのか教えていただきたいと思いますが、
日本という国は一枚岩ではないとおもっております。
なぜなら、1995(19年前だから貴方は生まれていないかと)年に起きた「阪神・淡路大震災」の時には、東北地方に住んでいる私は「ふーん。大変だね」、
位にしか思っていなかったからです。
ですので、復興については、西の方が本気で心配しているかはわからないということです。
日本人でも、分かり合えない人はたくさんいます。
そのために、貴方は存在するのだと思ってください。
「和田勉」という人が言っていましたが、
「国際交流などをやりたいのだったら、自分たちがどのような暮らしをしているのかを、自分たちのことをしらない人たちに紹介することだ」
と言っていました。
よって、被災地復興を目指すのであれば、大学は東北地方や関西地方ではなく、西の方に行き、ほかの学生や先生、教授たちに、自分が体験したことを語るといいと思います。
残念なことに、不遇な境遇で苦労している人たちは、「不幸せであること」を呟いて、死ぬまで呟き続けます。
私は、「幸せになるには自分で特訓しないといけない」と言いました。
震災は「過去のもの」です。
1995年である「過去」、「阪神・淡路大震災」がありました。
その地方の大学にいけば、「復興」の方法が体系的知識として学べるかもしれません。
一つのヒントが出てきた気がしますのこれくらいにしておきます。
歴史で勉強していると思いますが、震災以前に、戦争という災害が日本を襲っていることを思い出してみてください。
原爆が落とされた「広島」、「長崎」も、何十年かかって復興しています。
以上

ですので、私の提案としては、
「大学に行って勉強することについては、過剰な期待をするな」ということにつきます。
この13歳のハロワでは、ともかく「学校に行って○○」の人が多いです。
ですが、私が言いたいのは学校に行って何かを学ぶ、いや、「学べる」という過剰な期待は検討違いではないのかと言いたい
のです。
私の回答で、貴方の疑問が解けるかどうかは分かりません。
学生が教授やら先生の能力を凌駕することは普通にあります。
「悟り」というやつです。
悟りは、玉ねぎのように、何度も剥けます。
より上位の悟りを持っている人の意見というやつは、なかなか崩せません。
リッキーさんに、私を悟りの量やら質で「超えろ」とは言いません。
より重要視して欲しいのは、「感情に正直であれ」ということです。
上を目指せば目指す度、感情というものがなんて重要で、なんて不合理なんだろうと悩み苦しむ時がきます。
もし、貴方に部下ができた場合、部下の感情を逆撫でして仕事を進めさせるケースがあらわれた場合、
下克上されたり、仕事を一方的に辞めていったりすることがある場合があることを心に刻んでください。
ここがわからない。疑問がある。などなど、なんでもいいので、また書き込みをしていただければ、回答いたします。
また「幸せ」というやつは、特訓次第でなれるものです。
逆に言うと、ある程度、特訓しないと幸せにはなれません。
貴方の被災地復興の夢は、もし、宝くじで「3億円」当たってしまって、
お金に困らないから辞めてしまうような夢だったとしたら、
その夢は本当に貴方がしたかった夢ではなく、
働かないと死ぬからなんとか自分の自尊心や感情の面で有効的に働かせようとしているだけです。
私の場合、大手企業に勤めましたが、嫌になって辞めていく人を何人も見てきました。
「大手で働くことがカッコイイ!」ということは、今の時代ではなんら気分を高揚させるものではありません。

市紀です。
被災地の方なのですね。
大学の話を補足したいと思います。
私は被災地の西側に住んでいます。
ですので、仙台などに友達がいて、津波で流されて死んでしまった友達もいます。
3月11日に、その友達をうちに呼んでいたら死ななかったかもしれないと勝手なことを考えたりもします。
実際に、被災地に行ってみると、がれきの山に驚くことと、
自動車のナビゲーションで友達の家にいったらサラチになっていたことに愕然としております。
その上で、被災地のために大学で勉強する話をしましょう。
この話が私からの提案になります。
私は大卒ではありません。
ただ、社会に出ている分、甘えが少ないのが特徴かもしれません。
私が行った専門学校の先生とは、友達感覚で話をしますが、
こう言われます。
「学生の時代にそれができたかね?」と。
そうです。
社会にでると、学生時代にできなかった能力が突如現れるのです。
貴方は被災地にいるのですから、復興の方法に関して一つや二つの提案があるかもしれません。
ですが、学校でいくら能力が高くても、ただ喚いているだけではなにも変わらないのです。
よって、私が言いたいのは、「大学にいって学ぶ必要はあるのか?答えはもう自分のなかにあるだろう?」ということです。
私の専門学校の場合ですが、毎年、卒業研究をし、発表会でOBに叩きのめされるという習慣があります。
今年は仙台に向かっている途中、雪の影響で研究発表会には間に合いませんでしたが、私がいたら「なぜ、それをやろうとし
たのか?」という質問で学生を泣かせたことでしょう。
私が卒業した学校は、学生が学校に就職するというケースがあります。
その場合、卒業後は、大手電機会社で何年か揉まれます。
それから先生になるので、年をとった先生と若い先生とであまり能力に差がありません。若い先生の方が最新技術に秀でてい
たり、卒業してある会社に行った人間は先生を凌駕する能力があったりします。
私自身は東日本大震災で被災して現在も被災地の仮設住宅に住んでいます。被災したこともあったので被災地の街づくりに携わる仕事をしたいと思っています。そのためにも知識をつけるためにも大学に行って学びたいと思っています。しかし、質問内容や自分の考えに甘いところがあったと思います。ご指摘ありがとうございました。

市紀です。
一つの意見として捉えてください。
まず、「どの大学が良いでしょう?」
という質問はオカシイです。
被災地復興がしたければ、被災地にいって、被災地の人々の顔や声、状況などを判断し、自分の出来る範囲内でなにかしらの貢献をするだけで十分でしょう。
「どの大学が良いでしょう?」という質問は、
正直、私からしたら甘えてる状態だと捉えてしまいます。
どこぞすごい大学に行ったら、
被災地復興の一躍を担えるとでも思っているのですか?
被災地を復興させたければ、被災地で何ができるかを身をもって知ればいいだけです。
大学での勉強なんて必要ありません。
以上