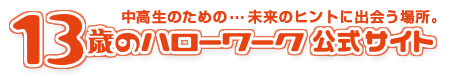HOME > もっと教えて!フォーラム > 仕事分野に迷ったらココ!「その他」の仕事 > 回答・コメントする(No.1272)
もっと教えて!フォーラム
回答・コメントする(No.1272)
-
いつも、子どもたちの疑問にお答えいただき誠にありがとうございます。
13hw編集部より、ご回答くださる際のポリシーに関するお願いです。
-
回答は、基本的には、その職業の方(または経験者、相応の知識を有する方など)にお願いしております。
しかしながら、なかなか回答のつかない質問もあります。
投稿されてから2週間経っても回答がつかない質問に関しましては、職業などに関係なく、ご回答のご協力をお願いしたいと考えております。 -
白書の皆様におかれましては、貴重な時間を割き、子どもたちの質問に丁寧にお答えくださったり、叱咤激励してくださって誠に感謝しております。
このようなお願いをするのは大変恐縮なのですが、勇気を出してこのサイトに質問を投稿してくれた子ども達に、よりよい情報を提供したいと考える当サイトの運営ポリシーをご理解・ご了承いただけますと幸いです。
 株でもうけた、損したって
株でもうけた、損したって
[Q] よく、株でもうけた、損したっていうのを聞きますが、どうしてもうかるのでしょうか。なんで、大人は株をかうのですか。
株を買うとどうして、会社のためになるのですか。
一度株を作って売ったら、その株は持っている人のものになるとすると、
会社にはお金がまわらないのではないのですか。
株をうったり、かったりするところでは、
どういう仕事をしているのでしょうか。
教えてください。

こんにちは。中学校の教育課程で「株式会社」というものを学ぶのかどうかよく知らないので、ごく簡単に説明しておきます。
株式会社とは、たくさんの人がお金を出し合って、ある利益を生み出す事業(物を作る・商売する・サービスを提供する…)を行うための仕組みの一つです。会社を作るために集めたお金を「資本金」と言いますが、ある人がその会社に資本金を提供した証明が「株式」だと思ってください(本当はちょっと違うのですが、それは自分で調べましょう)。
会社が予定通り利益を生み出せば、資本金を提供してくれた額に比例して、その利益を配分することになっています。これを「配当」といいます。一般には、会社の利益が大きいほど配当額も多くなります。配当は、ある基準となる日にその会社の株式を持っている人に支払われます。
例えば、私がある会社に100万円資本金を提供して、配当を1年で5万円もらった場合、5%の利益を得たことになります。今の銀行の預金金利が0.2%前後ですから、これはかなりお得かも知れません。そう考えた人の中には、私から100万円相当の株式を買い取って来年は自分が配当をもらいたい、と考えることもあるでしょう。一方、私は105万円より高い値段で株式が売れれば、配当をもらうよりも利益が出るかもしれません。
もし、来年はこの会社の業績が悪くなりそうだという場合、配当は当然減少するでしょうから、その会社の株式を買いたいという人は少なくなるでしょう=株式の価格が下がるかもしれません。
こうした、株式を「買いたい」「売りたい」という人たちの間を取り持つ会社が「証券会社」と呼ばれる企業で、実際に株式を売買する場所を「株式市場」といいます。
実際には、配当の多少よりも株式そのものの価格の上下のほうが値動きが激しい(ここが肝心)ので、株式を売り買いするとかなりの損得が発生することがあります。株式を売買する人はみんな「得をしたい」と思うのですが、なかなか簡単にはいきません。中にはギャンブルと勘違いしている人もいますから、注意が必要です。
でも、損をすることもある、ということを理解した上で、余裕のあるお金を株式に使ってみる(「投資する」)こと自体は、決して間違いではありません。でも、株式にお金を使う前に、まずはお金がどうやって世の中を巡っているのか、よく勉強してください。

エピソードⅢ
おっとっと、株で儲ける、株で損するとはどういうことかお話するのを忘れてしまいました。ここが一番あなたがお聴きになりたいところでしたね。ワザとじゃないですよ。
エピソードⅠで、海賊船と備品一式を買い揃え、水夫達を集めるのに、大変なオカネが必要でしたね。船長一人ではとても出せないオカネでしたから、町で余分なオカネを持っている人達から集めました。最初集めたオカネ全部のことを「資本金(しほんきん)」と言います。オカネを出してくれた人に、金額を書いた紙を渡しましたね。。「金貨1枚」とか、「金貨100枚」とか、出してもらったオカネの金額が書かれている紙を、「株券(かぶけん)」といい、「株」と略します。「株」を渡すとき、「勝手に増やしたり減らしたりしません」と全員に約束します。ここに「株で儲ける」とか「株で損する」ことが起こる秘密があるのです。
勝手に増やしたり減らしたりできないのですから、どんなに「海賊会社」が大きくなっても、最初の「資本金」の総額を越えた「株」はこの世に存在しません(「増資」とか「減資」とかは今は触れません)。
エピソードⅡの最後の所で欲しい人と売りたい人が集まっていた場所のことを「株式市場(かぶしきしじょう)」とか、「証券市場(しょうけんしじょう)」と呼びますが、ここで欲しい人が多いと「株」が足りなくなって値上りするとお話しました。足りなくなるのは、数が限られているからなのです。
さて、ここで考える人が出てきます。「足りなくなったら値上りするんなら、買い占めたら値上りするかな?」とか、「大慌てで大量に売りたいと言えば、皆不安になって必死で売るだろう。そうしたら安く買っておいて、皆が騙されたと気付いて買い戻そうとしたら、高く売りつけて儲けてやろう」とか「思惑(おもわく)」が渦巻くわけです。
エピソードⅡの最後にそうそう簡単に儲けることができないとお話したのは、「海賊会社」が儲かるかどうかということより、「思惑」で「株」の値段が大きく動くのが普通なので、ノーベル賞を貰うほど優秀な経済学者の先生が、必死に頭を絞って考えても、「株」で儲けるのは難しいからです。
「株」で儲けた人は、その人にしかない直感か、偶然儲かっただけのことが多く、いろいろな難しい計算をして儲かることは最初からわかっていましたなんて言って場合がほとんどです。ですから、オカネを私に預けていただければ「必ず」、「株」で儲けて上げますよなんて言ってくる人には、「嘘つけ!」と言って上げましょう。
長い間お疲れ様でした。

エピソードⅡ
さあ、海に出ました。もし、自分の母国と戦争中の国の商船を見つけたら、「お国の為だぜ、ヤッホー!」なんて叫んで攻撃し、敵が降伏したら、積荷をごっそり頂戴します。港に帰って、水夫達に約束した金貨を支払い、船体を修理して、船長自身の取り分を取った余りは、オカネを出してくれた割合にしたがって、多く出してくれた人には多く、少しだけの人には少しだけ支払います。
一度払えば終わりではありません。船長と仲間達が海の藻屑になるか、引退するまで続きます。
「株」とは、最初に港町の人達が出し合ってくれたオカネのうち、「あんたはいくら出した」と書いた紙のことです。オカネの総額の、100分の5を出した人は、「海賊会社」(この場合、「ハウルの動く城」のように、会社が船一隻に納まって動いています)の5パーセントの「株」を保有していることになります。あなたも歴史の授業で、「東インド会社」という言葉を習われたと思います。これも業務内容は「海賊会社」でした。
船と大砲が使えるうちは、ずっと海賊ができるので、ずっと獲物が手に入ります。水夫達の賃金を支払い、船長が自分の儲けを取り、破れた帆を張り替えたり、船体の側面に空いた穴を修繕して、砲弾や食料を買い揃え、船を買い換えるための「積立金」を用意したら、残りは再び「株主」に分配するのです。船長がこれで満足なら、この繰り返しが船長の引退まで続きます。引退した船長は海の見える高台のロッジで、ロッキングチェアーに揺られながらパイプをくゆらせて老後を送ります。
そして「株主」達はどうするかというと、船長の後を誰かが継いで、この「海賊会社」が続く限り、配当を受け続けることができるのです。誰も継ぐ人がいなければ、船も大砲も全部売り払い、オカネに買えて、「株」全体に対してどれだけの割合の「株」を持っているかによって分配します。これが会社の「解散」です。海賊船が海に沈んで何も残らなくなったら「倒産」です。
さて、最後に株の売り買いが何故行われるかですが、急にオカネが必要となった人や、「悪い夢を見た。次の航海でこの船は沈む予感がする」と思う人は、「株」をオカネに買えておきたいと思います。誰かに売りつけたいと思いますが、大声で「この株を買ってくれ」と叫ぶと「あの野郎!俺達は次の航海でオダブツだと言いふらしてやがるな」と憎まれたり、「海賊会社」の株を買おうという人が「危ないのかな?」と不安を感じて買うのを止めてしまうかも知れません。そこで「売りたい」と思う人と「買いたい」と思う人を引き合わせて、取引を素早くまとめる人が必要になってきます。そういう仕事が「株式仲買人」(もちろん犯罪行為でなく正当な取引を行っている会社しか扱ってきませんでしたので念のため)であり、現代の「証券会社」(こちらも同様)へと続いてきました。
「海賊会社」が今後益々儲けを配分してくれそうだと思う人は「株」を買いたいと思い、これ以上発展しそうにないから他の投資場所に移ろうと思う人は「株」を売りたいと思います。買いたいと思う人が売りたいと思う人より多いと、「株」が足りないので、「もっと高く買うぞ!」と言う人がでてきて「株価が上がる」のです。逆に売りたい人が買いたい人より多いと、「安くするから買ってくれ!」と叫ぶ人が出てきて「株価が下がる」わけです。
「株」を売り買いするのは、上手く行けば大儲けができるかも知れませんが、失敗して全て失うことになるかも知れません。成功した人の書いた本は飛ぶように売れますが、それは成功する人が失敗した人に比べてはるかに少ないからです。珍しいことだから皆が注目するのです。特殊な才能と強運の持ち主しか儲からないと考えていただいたほうが良いと思いますので、受験勉強を頑張ってください。

エピソードⅠ
ホリエモンの愛称で親しまれた、株式会社ライブドアの堀江貴文元社長のおかげで、株の売買だけで暮らしていける人の存在が広く世に知られました。中学生の皆さんがとっても気になって、高校受験のための勉強に身が入らないお気持ちもわかります。
この機会にごく大雑把にご説明してみます。ハロワのおやじさんのようなその道のプロの方からは至らない部分についてご指摘を受けるかも知れませんが・・・
字数制限があるので、エピソードⅠからの3部作になっています。受験勉強の一休みになれば良いと思いますので、脱力してお読みください。
最初のご質問は後で触れています。
なんで大人は株を買うのかは一概には言えません。買ったときの値段より高く売ってオカネを儲けたいという人が多いのですが、会社を買って、自分の理想を実現しようと思う人もいます。それが世の中の人皆の為になる理想の場合も、世の中の人を困らせる理想の場合もあります。ですから、株を買うことが会社の為になることもあれば、会社のためにならないこともあります。
一度株を作って売ったら、その株は持っている人のもので、お金は会社に回りません。それどころか、会社が利益を上げると、さらにオカネを配るのです。
何故か?それには株式会社の仕組みを知っていただかなければなりません。
ここでは経済学の解説でよく使われる例え方である「パイレーツ・オブ・カリビアン」に登場するような海賊を例にさせていただきます。
大航海時代、海賊が一旗上げようと思っても、手持ちのオカネが無いとします。でも、あいつは剣の腕でも誰もかなう者がいないし、頭の回転も速く、人をまとめる力もあるという評判が高ければ、「一丁船出するぜ!ついては船も買わなくちゃなんね~し、命知らずの荒くれどもも集めなくちゃなんね~、食料も武器もいるぜ!」と、港町の酒場なんかで呼びかけます。すると、今すぐ必要でないオカネをなんとか増やしたいと思う人達が、「あんたに賭けるぜ、船長!」とオカネを預けてくれます。そのオカネで海賊船を買い、大砲も砲弾も剣も食料も買いこんで、水夫や航海士、医師を雇います。
さあ、イカリを上げて、出航です・・・つづく