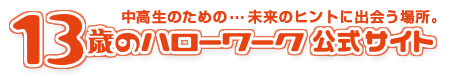HOME > もっと教えて!フォーラム > その他働くことについて何でも! > 回答・コメントする(No.4826)
もっと教えて!フォーラム
回答・コメントする(No.4826)
-
いつも、子どもたちの疑問にお答えいただき誠にありがとうございます。
13hw編集部より、ご回答くださる際のポリシーに関するお願いです。
-
回答は、基本的には、その職業の方(または経験者、相応の知識を有する方など)にお願いしております。
しかしながら、なかなか回答のつかない質問もあります。
投稿されてから2週間経っても回答がつかない質問に関しましては、職業などに関係なく、ご回答のご協力をお願いしたいと考えております。 -
白書の皆様におかれましては、貴重な時間を割き、子どもたちの質問に丁寧にお答えくださったり、叱咤激励してくださって誠に感謝しております。
このようなお願いをするのは大変恐縮なのですが、勇気を出してこのサイトに質問を投稿してくれた子ども達に、よりよい情報を提供したいと考える当サイトの運営ポリシーをご理解・ご了承いただけますと幸いです。
 出来るだけ多くの方にお答え頂きたいです!!
出来るだけ多くの方にお答え頂きたいです!!
[Q] 皆さんは
どのような仕事に就き、又どのような時に仕事のやり甲斐を感じますか?
簡単な質問ですが、私にとって働くという事は未知の世界なので、詳しく書いて頂けると嬉しいです。

こんにちは、れいこさん。
「出来るだけ多くの方にお答え頂きたい」とのことですので、私も回答してみますね。
●どのような仕事に就いているか
いろいろな仕事をしているのですが、肩書きにしているのは「ゲームデザイナー」です。
ゲームデザイナーというのは、ゲームのルールを考えたり、データを作る仕事です。
よくまちがえられるのですが、「グラフィックデザイナー」ではないので、
グラフィックの仕事はしていません。
特にここ10年くらいは、カードゲームのゲームデザインをしてきました。
子どもたちが(そして大人も)よくやっている、紙のカードゲームです。
ニンテンドーDSやプレイステーションなどのゲーム機のゲームデザイナーと比べて、
カードゲームのゲームデザイナーは、あまり多くはいません。
●どのような時に仕事のやり甲斐を感じるか
私は、ゲームデザインはクリエイティブな仕事であり、
製作したゲームは「作品」だと思っています。
ですので、その「作品」が評価された時が、いちばんやりがいを感じます。
「評価」といっても、完成した時に「いいのができた」と自己評価することもありますし、
メーカーの担当者さんに「いいのができましたね」と評価してもらうときもあります。
ネットの書き込みやブログなどでユーザーさんから評価してもらうこともあります。
一番明確なのは、売上という数字で評価されることです。
そのどれもうれしいのですが、やはり一番うれしいのは、イベントなどで
ユーザーである子どもたちから(もちろん大人からでも)、
「おもしろい」と言ってもらえることです。
ものすごく単純ですが、これに勝るやりがいはありません。

れいこさん
とても良い質問ですね。正にここを良く理解せずに社会に旅立つと
迷い子になってしまいます。
人は何故働くのか、まず原点から話を始めます。
①自分の自立のため
②自分の成長のため
①は言うまでもないでしょう。労働を提供し対価として賃金を得て経済的に自立すること。
一社会人としてこれまで育ててくれた親から自立し社会への義務と責任を果たすこと。
そう、すべてが自己責任の時代に入るのです。精神的にも自立していきます。
②これまでの家族・学校・地域など狭い社会から働く職場での様々の人の交流の中で
広い社会に入っていきます。つまりこれまでは家族や学校関係者など皆で貴方を守ってくれた
環境から自分のことは自分で責任を持つ環境に変わります。
職場で出会う同僚や上司・お客様を通じて貴方は仕事を覚えるだけではなく人間として
刺激を受けるのです。分かりやすく説明すると社会人としてゼロからスタートする貴方は
まず人の良いところ、つまり、Aさんのあの明るさ・積極性やひたむきな努力を自分もマネたい、どうしたらAさんの様になれるのだろうか?じっくりと日々の行動を観察してみよう。
話してみよう。聞いてみようなど目標になる人がいれば自分の成長につながるのです。
職場には沢山の人がいます。誰一人同じ人はいないのです。共通するただ一点は同じ会社に所属し会社のために貢献すること。同時に職場には反面教師もいます。ストレス社会では様々な人たちがいるのです。その全てを含めて貴方の成長に役立つ環境を職場は提供してくれるのです。その中で貴方の人生の師と生涯の心友にめぐり合えるかも知れません。
ここに働く意義があるのです。
次にどんな環境ならやる気になり、貴方の知らない才能が開花するかをお話します。
その条件はただ一つ。ひたむきに与えられた環境の中で努力することです。
人は誰しも自分の仕事ぶりを感謝されると俄然やる気に火がともります。はんがんさんが
おっしゃる様に”ありがとう”の一言で”あぁ、人の役にたっているんだ”と実感するのです。こうして職場でこつこつと努力していると新たなチャンスを与えられます。ここまで出来た、やれた、実績をあげた、次はもう一歩高い目標へと会社からその挑戦の機会を与えられるのです。こうして一つ一つ自信を積み重ねていくのです。自信は成長の原動力です。
最後まであきらめない人に幸運の女神は微笑むのです。
また更なるキャリアアップを考える時に”必要なら”専門学校や大学に進学し
専門性や必要な資格を取得しようとすることになるのです。
学びは一生です。その多くを仕事を通じて学ぶのです。
たった1回の人生です。やり直しはききません。
人生無駄なことは何もありません。すべてが貴重な経験でありその積み重ねが
貴方を創っていくのです。貴方も人も先のことなど誰もわかりません。
だから楽しく希望があるのです。夢を持つことはすばらしいことです。
そしてその実現のため日々精進するのです。
すべては貴方の気持ちの持ち様です。その気持ちが態度や表情に現れます。
また、考え方が行動に現れます。
他人との人間関係を円滑に保つ秘訣は”笑顔”と”人としての誠実さ”です。
それを一生忘れないでください。
人の進路は環境と偶然に左右されます。
それを天や運に任せるのではなく自ら積極的に人生を切り拓く
その積極性が大事です。
最後になりますが私の話をします。
経験をコツコツと積み重ね、この年になり、ようやく皆さんにアドバイスできる
様になりました。ここまでの人生を振り返ると、それは正に周りの皆様に支えられてここまで
歩んでこれたと思っています。大変感謝しています。
これからは私が皆さんに恩を返す時だと思っています。
これからも日本のために貢献していきたいと考えています。
これからの日本を託す若者の支援をこれからも続けて参ります。
これこそが私たち団塊世代の努めだと思っています。
後15年ぐらいはバリバリ働きたいと考えています。
振り返ると全くシナリオのないドラマでした。
私が高校生のころこの様な人生を送ることなど想像も出来ませんでした。
一つだけ自信をもっていえることはあきらめなかったことです。
為替ディーラーからキャリアカウンセラーへ
そして私の道はまだまだ続くのです。
Do your best and it must be first class.
ベストを尽くせ。そして一流であれ。
を日々実践してきました。そしてそれを継続しています。

こんにちは。あなたはまだ働いたことはないかもしれませんが、例えばある人にお遣いを頼まれたり、電車でお年寄りに席を譲った経験はあると思います。そういうとき、相手から「ありがとう」とひとこと言ってもらえると、とても嬉しい、そう感じませんか? もちろん、あなたは「ありがとう」なんて言ってもらうためにそんなことをしたわけじゃないけど、でもやっぱり嬉しい。それが人の素直な心のあり方だと思います。
仕事のやりがいなんて、働く人が百人いれば全員違うかもしれませんが、私にとってはそういうささやかな幸せを感じることができるとき、仕事をする喜びをもっとも強く感じます。
ちなみに、私はある素材産業メーカーに就職して、工場の総務→営業→出向その1(系列商社で営業)→出向その2(系列メーカーで営業企画)という仕事をしてきました。この業界では極めて珍しい職歴です。いわゆる出世街道とは全然縁遠いけど、私の年齢でこの業界のほとんど端から端まで経験するのは、たぶん他の人には難しい。必ずしもやりがいではありませんが、こういうところに喜びを感じることもできます。
今、ハワイで活躍中の「すばる」望遠鏡の製作経過に関するおそらく初めての一般向け報道発表は、私が担当しました。世界の海で活躍中の探査船「ちきゅう」甲板上の重要設備や推進部は、私が扱った製品で作られています。こういう部分は、この業界ならではの喜びでしょう。当社が関係するある行事にやって来た当時の首相がお手洗いにいく時、MPの皆さんと一緒にトイレの不審物捜索をやったり、首相にサインをねだりに来た女子社員(笑)を整理したり、という経験も、私の職歴ならではのものです。
でも、そんな極端な例が毎日転がっているわけではない。今日の仕事を無事に果たせたと感じられるちょっとした一瞬が、毎日ではないけどきっとあります。それが何かを説明することは、とても難しい。たぶん人によって大きく違うからです。
あなたが将来仕事に就いたとき、いつか初めてその瞬間が来ると思います。そのとき「私もこうして働いているんだ」と実感できるでしょう。たぶん、それがあなたにとっての仕事のやりがいになるでしょう。
…ちょっと観念めいた答えですが、この答えはあなた自身に、ぜひ見つけていただきたい。そう思います。