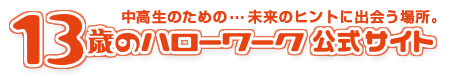HOME > もっと教えて!フォーラム > 快適な住環境を作る「建築・インテリア」に関わる仕事 > 回答・コメントする(No.5674)
もっと教えて!フォーラム
回答・コメントする(No.5674)
-
いつも、子どもたちの疑問にお答えいただき誠にありがとうございます。
13hw編集部より、ご回答くださる際のポリシーに関するお願いです。
-
回答は、基本的には、その職業の方(または経験者、相応の知識を有する方など)にお願いしております。
しかしながら、なかなか回答のつかない質問もあります。
投稿されてから2週間経っても回答がつかない質問に関しましては、職業などに関係なく、ご回答のご協力をお願いしたいと考えております。 -
白書の皆様におかれましては、貴重な時間を割き、子どもたちの質問に丁寧にお答えくださったり、叱咤激励してくださって誠に感謝しております。
このようなお願いをするのは大変恐縮なのですが、勇気を出してこのサイトに質問を投稿してくれた子ども達に、よりよい情報を提供したいと考える当サイトの運営ポリシーをご理解・ご了承いただけますと幸いです。
 インテリア・空間造形に関する仕事について大学では何学部?
インテリア・空間造形に関する仕事について大学では何学部?
[Q] 高校1年生の女の子です。
私は、部屋やレストランなどのデザイン(内装?)を見るのが好きです。
将来はそのようなことを考える仕事に就きたいと思います。
4年制大学で学ぶとしたら、何学部ですか?
調べてみたら自分だと建築より住居学かと思ったのですが・・?

こんにちは。追加の質問をいただいていますので、分かる範囲で簡単にコメントします。
空間心理学といっても、その専門の講座がある大学は、私の知るかぎりそれほど多くありません。大学の心理学科を調べると、いくつか存在するようです。
空間心理学以外にも、「空間のあり方が人の心や行動にどのような影響を与えるか」というテーマには、様々な角度から学ぶことが可能です。建築デザイン系の学科の中にはかなり実践的な講義をするところもありますし、純粋な学問としてなら、心理学の他にも生理学という選択肢だってあります(ただし、本当に純粋学問なので、建築デザインに役立つかといわれると、ちょっと迷います)。私の知らない分野もきっとあることでしょう。
あなたが普段生活する場所は、何らかの形で空間デザインが意識されています。ほんの少しだけでいいから、「どうしてこういう場所になっているのかな?」と気に留めて街を歩いてみてください。きっと、いろいろ新しい発見があると思います。しばらくの間続けてみて、何か具体的に興味を引かれることが見つかったなら、いちど学校の進路指導の先生にそのことを話してみましょう。あなたの知らない進路をいろいろ教えてもらえるかもしれません。
丁寧な回答ありがとうございます(*^-^*)
建物といっても様々な種類があること、様々な視点があることが分かり深く考えるきっかけになりました。今まではお店しか見ていませんでしたが、学校など他の様々な建物に興味が沸いてきたのでもっと視野を広げたいです。
視点としては、デザインも気になりますが、空間心理を学んでみたいと思いました。
空間心理は、どこで学べますか?

こんにちは。あなたは「建物の内部の空間をデザインする」仕事に就きたいのでしょうか。その前提でコメントしておきます。
ここで、単に建物といってもいろいろな種類があることに、留意しておきましょう。人が生活する場所(住宅)はもちろんですが、そうでない場所(非住宅)もたくさんあります。学校や病院、レストランにショッピングセンター、美術館や会社のオフィス、さらに空港のロビーや大工場などなど。もちろん、その全てをデザインできるスーパーマンもいますが、大半の方々は自分の専門の(または得意とする)分野を持っていて、それをお仕事の基盤にされています。あなたもある程度は自分がどんな建物をデザインしたいのか、考えておくことをお勧めします。
また、建物の内部空間のデザインといっても、
○家具や壁などの視覚的なデザイン(配置・色彩など)を考える
はもちろん、
○適切な照明や空調(冷暖房や排気)を考える
○地震や火事などの災害に強い空間になるように、空間のあり方を考える
○人の動き方や大勢の人々の「流れ」を考える
などなど、様々なポイントがあり、それぞれが互いに関係しながら、一つの空間をデザイン(設計)しています。
これらを「建物を作る仕組み」として考えると主に建築学や工業系デザインとして、「人の感じ方」として考えると、例えば空間心理学や美術系デザインなどとして、それぞれ学ぶことになります。つまり、同じ現象を考える時に、視点の違いに応じて、学問領域が違うということです。
日本では、こうした「学問間の壁」が諸外国に比べて高い傾向にあるため、いったんある学問を学ぶと、他の学問に首を突っ込むのが難しいことがあります。もちろん、あとから修正は利きますが、最初にある程度あなたが「どういう視点で空間の設計をしたいのか」を考える必要があります。今はちょっと難しいかもしれませんが、自分が空間デザインのどこに興味があるのかを、少しずつ考えておきましょう。
日本は欧米よりも建築物の(資格的・感覚的)デザイン重視の傾向が強く、実際空間デザインは美術系の建築デザイン学科でも十分学ぶことができます。一方で、建築物そのものの性能が問われる場面も増加しており、建築学としての空間デザインを学ぶことは、今後重要になるでしょう。個人的にはちゃんと建築士資格を取得することをお勧めしますが、「この喫茶店の壁の色は何にしよう?」といったお仕事には、必ずしもこの資格は必要とはされません。
繰り返しになりますが、あなたがやりたい仕事の内容によって、学ぶべきことも、必要となる資格も異なりますので、もうしばらくの間、じっくり考えてみてください。