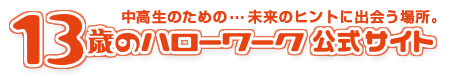HOME > もっと教えて!フォーラム > 「13歳のハローワーク」の利用法 > 回答・コメントする(No.7235)
もっと教えて!フォーラム
回答・コメントする(No.7235)
-
いつも、子どもたちの疑問にお答えいただき誠にありがとうございます。
13hw編集部より、ご回答くださる際のポリシーに関するお願いです。
-
回答は、基本的には、その職業の方(または経験者、相応の知識を有する方など)にお願いしております。
しかしながら、なかなか回答のつかない質問もあります。
投稿されてから2週間経っても回答がつかない質問に関しましては、職業などに関係なく、ご回答のご協力をお願いしたいと考えております。 -
白書の皆様におかれましては、貴重な時間を割き、子どもたちの質問に丁寧にお答えくださったり、叱咤激励してくださって誠に感謝しております。
このようなお願いをするのは大変恐縮なのですが、勇気を出してこのサイトに質問を投稿してくれた子ども達に、よりよい情報を提供したいと考える当サイトの運営ポリシーをご理解・ご了承いただけますと幸いです。
 「13歳のハローワーク」は悪書でしょうか?
「13歳のハローワーク」は悪書でしょうか?
[Q] 私は最近「13歳のハローワーク」を読みましたが、その偏見、偏向、独りよがり、高慢な内容にビックリしました。
作家など自分に関連した職業の内容や、なぜか「鵜飼い」など個人的に興味があると思われるような内容に関しては非常に詳しく書いてはあるものの、それ以外(おそらく自分に興味、関心のなさそうな)の内容はありきたりのことやうわべだけのことしか書いてなく、また住宅展示場の案内係を「しつけのいい犬でもできる」と差別的な内容で表現したり、なぜか最後に「ここまでの職業に興味をもてなかった君に」といって「戦争関連の職業」を紹介したりと意味不明であぜんとする内容もあり、とても多くの人に勧められるような中立性がみられませんでした。
私にとっては読んでいて不快、頭にすらくる見るに堪えない内容でこんなものを勧める人たちも「おかしい」と思いますが、皆さんはほんとうにこの本を自信を持って推薦してるんでしょうか?
私はこの本を中学生の時に親にすすめられ、読んでみました。
その時の私は、将来の夢など真剣に考えたことはありませんでした。
今楽しいこと、やりたいことをこの先もずっと続けていけたらいいのに
位にしか考えていませんでした。
しかしこの本を読んだことにより、考えが変わりました。
まず、仕事の多さに驚いたものです。
この本にのっている職業もわずかであることは今は承知しておりますが、
その時はこの本にのっているものでもとても多いと感じましたし、
たくさんの仕事がある、ということをしったことにより
将来を漠然と考えていては将来必ず困ることになるのではと考えるようになりました。
私はそこから、将来の仕事について、それまでよりもよく考えるようになりました。
そこで少し興味のある仕事について、インターネットなどで調べてみました。
すると、さらに細かく、多くの仕事がでてきたのでまた驚きました。
たしかに、著者の主観がこの本には多くあり、
ページ数も偏っているかもしれません。
しかし、この本の本当の大切さは
子供に将来に少しでも目を向けさせることにあるのではないかと
私は自分の経験から考えます。
この本はたくさんの仕事があることを子供に理解させ、それをさらに深く調べていく
きっかけになる本であると思います。
村上龍さんという方は非常に独善的な人です。他の方が言われているように中立的ではないですね。一つの職業について偏りがないように詳しく調べないといけないのに、それも怠っているように見えますし、鵜呑みにするのは危険かと思います。
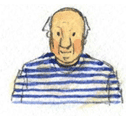
こんばんは池田さん。貴方は幾つですか?
名前の付け方や質問の内容から考えて中学生は無いですよね。
まあ、良いですが(笑)。
さて、他の方も書いていますが、私はこのサイトや本を
世に紹介した村上さんは本当に凄いと思います。
また、この本の恩恵を受けている方も沢山いるでしょう。
書籍の内容は人が書いたものですから、好き嫌いはありますよね。
でも何か最初のきっかけがつかめたら、いまはインターネットで
更に他の人が書いた情報も読むことができます。
最初のキーワードさへつかめれば、いいのではないでしょうか。
私は世の中にこれだけ沢山の仕事があるという事実を
知る事ができた子供達は本当に幸せだと思います。
私も子供の頃にこのような一覧を是非見たかったです。
興味のある職業に関して詳しい記述がありますし、
知らなかった職業に興味を持って自分のやりたい事が
見つけられるかも知れません。
また、自分の興味のある職業にはどのような能力が必要か
どんな道があるのかの一端を知る事ができるのです。
大人の方々は誇りをもって自分の仕事を紹介し、
子供達に仕事の素晴らしさを伝えようとされています。
素晴らしい人たちが集まるコミュニティだと思います。
何事も良いところがあれば、悪いところもあります。
私は良いところの方が多いと思っています。
また、そう思っている人が多いからこそこれだけ人が集まって
居るのではないでしょうか。
もちろん、人によっては悪いところがどうしても気になるでしょう。
100%の人が満足するものは無いですから。
良いところをうまく使えればそれでいいのではないでしょうか。

こんにちは、池田さん。
「ゲームプランナー」の記述についてあれこれ言うのは、重箱の隅をつつくようなもので、
「13歳のハローワーク」の意図とも、池田さんの質問の意図とも
大きくずれてしまうとは思いますが、ちょこっとだけ。
『なんといっても最大の魅力は、ゲームが産声をあげてから世に出るまでの
一連の流れを目の当たりにできることだ。』
この一文については、私はむしろ、現場の生の声であると感じました。
ゲームプランナーというのは、製作工程では一番初期から作業をはじめています。
ゲームの「種」をまくような仕事です。
その「種」である企画書や仕様書を元に、多くのクリエイターが素材をつくり、
素材を組み合わせ、ゲームを完成させていきます。
ゲームとしての形を持っていなかった「アイデア」の状態のものが、
どんどん形を与えられていくのを俯瞰的に見れるのは、
ゲームプランナーやゲームディレクター(社長であることもあるでしょう)の特権です。
少なくとも「ゲーム制作現場を取材するジャーナリスト」では味わえません。
なぜなら、彼は「種」をまいてないからです。
「ゲームツクールを使えばアマチュアでも体験できる」というのは、
確かにそうだと思います。
ですので、私は、ゲームクリエイターを目指す人に対して、
「ツクールでいいので、実際にゲームを作る」ことをお奨めしています。
「実際にゲームを作る」ということが、ゲームクリエイターには重要だと思います。
『テレビゲームが好きだからといって、
ゲーム作家やゲームプログラマーになれるわけではない。』
この一文は、
「テレビゲームが好き」と「テレビゲームを作るのが好き」、
その2つには大きな違いがあることを教えてくれると思います。

D作さん、こんばんは。
D作さんの意見や、物の捉え方は、とても良いと思います。
大人から与えられるものを無批判に受け入れてはダメです。
本が気に入らなかったのなら、参考にしてはいけません。
気に入らない本でもキチンと読んでいる忍耐力にも感心しましたけど・・・。
ここでは、沢山の大人が自分の職業について語っていますが、
すべての大人が、村上龍と同じように、上から目線で、独りよがりです。私も含めて。
でも、
それこそが現場で働く大人たちの生の声です。
色々な現場の声が聞けるのは、とても得な事です。
沢山の大人の個人的な意見に触れて、
D作さんにとって、個人的に「良い物」を見つけてください。

こんにちは。質問者が実際に中学生であるという前提で、コメントを寄せます。
「13歳のハローワーク」という書籍の真の価値は、「こういう類いの本を初めて出版した」という点にあると私は考えています。極端に言えば、内容なんてどうでもよろしい。こういう本を出すことが世の中に求められていると誰かが企画し、それを実行した。このことが重要なのです。この後に似たような本が続かない、ということが、この本の客観的な評価を示しているのかもしれません。これだけ出来がよければ、確かに後続はたいへんです。
国語辞典を読み比べるという、とても贅沢な趣味があります。あなたは学校の図書館に行って、同じ単語を複数の辞書で引いてみるといいでしょう。概ね同じことを書いているようでも、辞書によって、説明の順番が違ったり、引用文が違ったり、時には意味の解釈や(漢字の場合)読み方すら違ったり、いろいろです。例えば「判官」を調べると、よくもまぁこれだけ違うこと。なぜそうなるのか、とあなたはよく考えるべきでしょう。
一見客観的に見える国語辞典ですらこうなのです。ましてや、職業を紹介するという本に、著者や編集者の考えが反映されない方がむしろおかしい。それを自分の意見と違うという理由で否定する狭い視点ではなく、「なぜ著者はこういう風に書いたんだろう?」と考えることが、この手の本を読むいちばん大切なことだと思います。内容の善し悪しはともかく、この本はそれを考えるだけの価値を持っているから、多くの人に支持されているのです。
ちなみに、私の知り合いのゲームクリエーター氏は、この本におけるゲーム製作紹介の記述を絶賛しています。私はゲームをまったくしないのでよくわからないのですが、「よくぞ書いてくれた!」なんだそうです。
ゲーム制作だけでなく、ある特定の職業の詳細をマニアックに示すのがこの本の目的ではありません。そこまで興味のある人は、早く専門書を探すべきです。ゲームの用語を借りるなら、その職業(群)の「世界観」を紹介することがこの本の使命であり、そこに執筆者の主観が入るのは当たり前です。だから大人が読んでも面白いんですよ。
あなたはもう一度この本の「はじめに」をよく読んでみるべきでしょう。そこに書いてあることに価値を感じないなら、あなたはこの本を読む必要はありません。それは本の善し悪しではなく、あなた個人の問題でしょう。
まこさん
早速のご回答ありがとうございます。
やはり大なり小なり「主観が強い」というのは調べたところ非常に多くの
方(というよりほとんどの方)が思われているようです。
「ゲームプランナー」に関する記述もひどいものでしたね。
そもそも「ゲーム(ほかに漫画、アニメ)が好きな人は多数いるだろうが~」
とわざわざ別欄にして「どうしてもというなら~」という風に書いていましたが
わざわざそうしてるのも意味不明でした。
そもそもゲームの職業人といっても「プランナー」のほかに「プログラマー」
や「サウンドコンポーザー」「CGデザイナー」など、多数の職種があるにも
かかわらず乱暴なくくりにしていて「まじめにやってんのか」とすら思いました。
>『なんといっても最大の魅力は、ゲームが産声をあげてから世に出るまでの
一連の流れを目の当たりにできることだ。』
>
>という一文があり、その部分には共感できました。
>「仕事のおもしろさ」を伝えるという部分では、いい記述だと思います。
私にはこの分も?と思います。
目の当たりにするなら別に「ゲーム会社の社長」やあるいは「ゲーム性セク現場
を取材するジャーナリスト」でもいいんじゃないでしょうか?
「目の当たりする」なら高機能なゲームツクールとかを使えばアマチュアでも
体験できますし、それを「やりがい」としているゲームプランナーの声を
実際に耳にしたのか?と思います。
>この本は中立性や客観性を重視した事典ではなく、まぎれもなく村上龍氏の「著作」です。
>村上龍氏の作家性があちこちからにじみでています。
>事典や辞書やカタログのつもりで読むと、そういった作家性が気になるかもしれません。
職業紹介に「作家性」なんて必要があるのでしょうか?
「13歳」への職業紹介(の第一歩)を自分の趣味趣向を丸出しにした
中には偏見差別も含まれているような本でするなんて何か「受け手に対する
配慮」というものが全くないように思います。
それを「推薦図書」としてい公に広めているのも、ちゃんと内容を検討して
ふさわしいと考えたのか(単に流行ってるからその流れに乗っただけなんじゃないか)
と首をかしげます。
ちなみに管理者の方が目にされると思いますので書いておきますが、
利用規約には「13歳のハローワークおよび村上龍を批判、否定する内容の
書き込みをしてはならない」という内容は一切ありませんでしたので
念をおさせていただきます。

こんにちは、池田さん。なかなか挑戦的な質問ですね。
「13歳のハローワーク」が、著者村上龍氏の主観が強いという感想は、私も同感です。
ある職業の記述が、実際にその仕事についている人から見れば、
あまり十分な内容になっていないというのも同感です。
私はまっさきに「ゲームデザイナー」の項目を探したのですが、
「ゲームデザイナー」はなく、「ゲームプランナー」があり、
その内容もあまり満足できるものではありませんでした。
とはいうものの、ひとこで「ゲームプランナー(デザイナー)」と言っても、
さまざまな仕事のスタイルがあり、それをわずか半ページほどの文章で、
すべての人が満足できる記述にするのは難しいのです(無理です)。
職業についての他の本でも「ゲームプランナー」を調べてみたのですが、
どの本を読んでも完全に満足できるものはありませんでした。
ただ、「13歳のハローワーク」の「ゲームプランナー」には、
『なんといっても最大の魅力は、ゲームが産声をあげてから世に出るまでの
一連の流れを目の当たりにできることだ。』
という一文があり、その部分には共感できました。
「仕事のおもしろさ」を伝えるという部分では、いい記述だと思います。
***
(本の)「13歳のハローワーク」は500以上の職業が紹介されており、
どうしても「仕事の百科事典」と見られがちです(本のサイズもそんな感じです)。
しかし、全編を通して読むとよくわかるのですが、
この本は中立性や客観性を重視した事典ではなく、まぎれもなく村上龍氏の「著作」です。
村上龍氏の作家性があちこちからにじみでています。
事典や辞書やカタログのつもりで読むと、そういった作家性が気になるかもしれません。
小説や評論を読んで、「これはおかしい。自分はこう思う」と感じるように、
「13歳のハローワーク」を読んで池田さんがいろいろ感じるのは、自然だと思います。
なお、この「13歳のハローワーク」の公式サイトの各職業紹介のコーナーでは、
原典の記述に加え、さまざまな追加情報が加えられています。
そうすることで、本の「13歳のハローワーク」より、より客観的になっています。
また、最近のリニューアルで、本には書かれていない仕事についても、
新たに紹介されています(職業の種類が2倍になっています)。
池田さんが求めているバランスにより近くなっているんではないでしょうか.