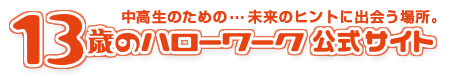HOME > もっと教えて!フォーラム > 生命を扱う「医療・福祉」の仕事 > 回答・コメントする(No.8684)
もっと教えて!フォーラム
回答・コメントする(No.8684)
-
いつも、子どもたちの疑問にお答えいただき誠にありがとうございます。
13hw編集部より、ご回答くださる際のポリシーに関するお願いです。
-
回答は、基本的には、その職業の方(または経験者、相応の知識を有する方など)にお願いしております。
しかしながら、なかなか回答のつかない質問もあります。
投稿されてから2週間経っても回答がつかない質問に関しましては、職業などに関係なく、ご回答のご協力をお願いしたいと考えております。 -
白書の皆様におかれましては、貴重な時間を割き、子どもたちの質問に丁寧にお答えくださったり、叱咤激励してくださって誠に感謝しております。
このようなお願いをするのは大変恐縮なのですが、勇気を出してこのサイトに質問を投稿してくれた子ども達に、よりよい情報を提供したいと考える当サイトの運営ポリシーをご理解・ご了承いただけますと幸いです。
 児童専門の精神科医について
児童専門の精神科医について
[Q] ▼児童専門の精神科医に
なる事は可能ですか?
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
はじめまして
進路について悩んでいる高校生(♀)です
私は今精神科医を目指しています
ただ…子ども専門の精神科医になりたいと思っています。
子どもの悩みを聞ける仕事につきたいと思いスクールカウンセラーなどの仕事も
考えてみたのですが、
子ども達が気楽に行き来したり悩みを話せるような場所(病院)を作りたいと思っているんです
なので臨床心理士やスクールカウンセラーなどの職業だと実現するのは難しいのかなと…
あと精神科医を目指すなら外科医などの医者を目指す人達
並みに受験勉強はしなくちゃなれないですよね?
※ネットで調べてみたのですがいまいちピンとこなかったので質問させていただきました。
良かった回答よろしくお願いします。
あきちゃんで〜すさん、
通りすがりの大学教員さん、
回答ありがとうございます!
自分の将来の事なのでもっとじっくり考えてみます。
あと大学のオープンキャンパスにも行って志望校も
しっかり決めたいと思います:)
本当にありがとうございました。

あきちゃんで〜す先生が既に過不足なくお書きになっていますが・・・
医師免許と臨床心理士のダブルライセンスを取得することは,通常の4年制大学を卒業して取得を考えるより,ややラクかもしれません.
医学部は6年制なので,卒業するときの学位は「医学士」ですが,慣例上「修士」相当と見なされます(ちなみに昔は卒業医の学位も『医学修士』でした).そのため,臨床心理士資格を取得する場合,指定大学院に進学する(=修士号を得る)必要はなく,2年間の臨床経験があれば資格申請が可能です.
法令・資格などは別にして,医学をしっかり学ぶことは,メンタルヘルスの診療を専攻する上で,大変役に立つと思います.ありきたりな表現ですが,心と体は密接につながっております.「心療内科」という分野があるくらいですからね.また,大学院生の指導などをしていると感じるのですが,「生き物」としての人間のとらえ方が,医師と非医師の間では違うように思えます.上手く説明できないのですが,誤解を恐れずに言うなら,医師は「体で理解して」おり,非医師は「頭で理解して」いるような気がします.どちらがいいかといえば,私は前者の方が好ましいと思うのですが,これは私が医師であるための欲目かもしれませんので,異論反論新説はいろいろあるでしょう.
でも間違いなく言えることは,外科だの内科だの小児科だのを体系立てて勉強することは,あなたのキャリアの得にこそなれ,重荷になることはないでしょう.従って,総合的にメンタルヘルスを取り扱うのであれば,医師であることはbetterなのではないかと思います.
将来のキャリアパスを考えるにしても,「資格の後ろ盾のない」広場のようなものを作るよりも,例えば診療所に併設された施設などを作る方が現実的です.たとえば私の近所では,小児科のクリニックに託児所を併設する,という事例があります.
ということで,とりあえず医学部を目指してみるのは如何でしょうか.これは勧誘です(笑).

るんっ◎さんへ
通りすがりの大学教員さんも書いていらっしゃるとおり、臨床心理士は「国家資格」ではありません。もちろん、現在の心理職において、権威のあるものではありますが、あくまでも「民間資格」です。
ですから、類似したような資格はたくさんありますし、開業するときの「免許」になるわけでもありません。民間の「△△相談所」だって、臨床心理士の資格でない方はたくさんいらっしゃいますよ。
臨床心理士と医師免許の兼ね合いについては、
「医師免許を取得後、二年以上の心理臨床経験を有する者」に受験資格を与えるという規定になっています。
臨床心理士資格取得までの通算の養成・教育・研究期間は、「第1種指定大学院」・「専門職大学院」へ入学した場合は最短で7年間(学部課程4年間+大学院課程2年間+資格審査受験年度。資格交付は8年目)、「第2種指定大学院」へ入学した場合は最短で8年間(学部課程4年間+大学院課程2年間+有給臨床実務経験1年間+資格審査受験年度。資格交付は9年目)を要します。
臨床心理士が国家資格でないことについては、結構大きな論争があり、将来的には、制度の変更もあり得ます。
回答ありがとうございます!
知らなかった事だったので
とても参考になりました☆
ありがとうございます。
また質問になってしまうんですが…
▼臨床心理士の資格だけを取った場合
相談所のような場所を自分でつくる事は出来るんですか?
▼精神科医と臨床心理士の両方の資格を取りたい場合
医学部に入学し卒業後に大学院に通って
その後臨床心理士の資格を取るんですか?
申し訳ないですが
回答よろしくお願いします

あきちゃんで〜す先生>
早速のレスポンス,誠にありがとうございます.
保険点数で算定できる「通院精神療法」は,医師が行わなければなりませんが,現実には同様の診療を「心理療法」として,臨床心理士が行っているケースが見られるようです.
患者さんと話をする,というのは医療行為としての線引きが難しい行為で,以前からあった「看護師が注射をするのは違法だ」とか,「医学生が患者さんの診察をするのは違法だ」という論争に似たものがあります.ごくごく厳密に解釈をすると違法であるが,実際には行われている・・・いわゆる建前と現実のギャップが存在するところです.
私の意見としては,「カウンセラーが心理療法を行うのは越権行為だ」というのは,あまりにも杓子定規なものの考え方だと思います.悩み事の相談に乗ってくれる友達だって,愚痴を聞いてくれる飲み屋のオネエサンだって,詰まるところは(意図的にせよ意図的でないにせよ),カウンセリングの延長線上にあるものなのではないでしょうか.ですから,ただ「医師免許」という紙切れ一枚で「医療行為だから」と排他的に決めつけることに違和感を感じるわけです.
ところで,臨床心理士は民間資格ですが,かなりの難関のようです.資格も永久資格でないために,学会参加や論文執筆など,資格維持のために相当の努力が必要なのだそうですね.そのような専門性を持った資格なのに,病院の中では「精神科医の指導の下」という条件が付けられてしまうのは,何となく残念な気がします.
かくいう私のイメージする臨床心理士の像は,松岡圭祐氏の「千里眼」シリーズに出てくる,岬美由紀さんですかね.まぁフィクションですけれど.

とおりすがりの大学教員さんへ
ありがとうございました。
私がかなり以前に読んだ本で(精神科医の方が書いた本です)、「心の病を治すというのは、治療行為であるから、それをカウンセラーが行うのは、越権行為であり、法律違反である」というような内容が含まれていました。あくまでも「相談にとどめるべき」と。
医師に限らず、「免許」が必要な職種について、その職業以外の人は、それほど詳しい認識を持っているわけではないと思います。
たとえば、同じ「教える」でも、学校なら教育、塾なら「営業」とみなされ、印刷物のコピーなどもべつの法解釈が適用されます。
そのように、社会は「法」で動いていて、それぞれの守備範囲があることがわかって、
るんっ◎さんも、参考になったのではないかと思います。

職業に対するイメージの問題ですが・・・
児童であるなしに関わらず,精神科は「悩み相談所」ではないんです.
精神科で取り扱う病気の第一位は,統合失調症(schizophrenia)です.児童にはほとんど有病者がいませんが.
子供では,自閉症や,精神発達遅滞が主たる対象になると思います.これらの子供達は,そもそも悩みを自発的に発露することが出来ない事が多く,正直会話を成り立たせることすら困難な場合が多いです.従って,あなたが「悩みを聞く」ということを主眼に精神科医を目指すと,現実と理想のギャップに戸惑うかもしれません.そこで,いわゆる「カウンセリング」などを行うことを想定されているのであれば,臨床心理士なども視野に入れるといいかもしれません.いわゆるスクールカウンセラーですね.
ただし,精神科医は,カウンセリングを行うだけでなく,薬を処方したりすることも出来ます.すなわち,心の病気に対処するツールを,他の職種より多く持てるわけです.これは精神科医の持つ大きな利点かもしれませんね.
ちなみに,精神科医で臨床心理士の資格を持っている方もいらっしゃいますよ.

次の文は、某国立大学の児童精神科からの抜粋です。参考になさって下さい。
精神科の研修システムの中に入って研修を受けていただきます.児童精神科医療に従事するためには,一般精神科の知識・経験が不可欠あり,また,精神保健指定医の取得が多くの場合に必要であります.
入局して2年間は,大学病院での研修です.一般精神科が主の研修となります.
入局した後は,毎週木曜日に行なわれます児童精神医学グループの症例検討に参加することが可能です.また,交代で児童患者の予診をとり,初診診察に同席していただきます.入院患者についてはスタッフの指導のもと,主治医として診療を行なっていただきます.
2年目より正式に児童精神科グループへの所属が可能です.
大学病院での研修の後,2年間は大学外の病院での研修です.その間も施設により,児童精神科診療を行なうことは可能です.
その後,希望により,児童精神科関連施設での勤務を行なうこととなります
あきちゃんで〜すさん、
回答ありがとうございます◎!
参考になりましたっ★
※…って事は児童専門の精神科医に
なる事は出来るって事ですか?
また質問してしまい申し訳ないです、

十和さんへ
立派な志だと思います。頑張って下さい。
詳しいことは、お医者様の回答者の方が答えて下さると思いますが、
医師の診療科目は、入学後に研修などを経て決めるもので、他の学部の学科のように、入学前に「○○科を受験する」と決まっているわけではないと思います。
ですから、精神科を目指している人も外科を目指している人も、同じ試験を受けて入学するのだと思います。
教員としての一般常識からいえば、カウンセラーより精神科医のほうが、子どもにも親にも、ずっと「敷居が高い」ですよ。
気楽に精神科に通う…難しい命題だと思います。