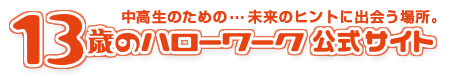HOME > もっと教えて!フォーラム > 世の中に情報を発信「放送・出版・マスコミ」の仕事 > 回答・コメントする(No.8850)
もっと教えて!フォーラム
回答・コメントする(No.8850)
-
いつも、子どもたちの疑問にお答えいただき誠にありがとうございます。
13hw編集部より、ご回答くださる際のポリシーに関するお願いです。
-
回答は、基本的には、その職業の方(または経験者、相応の知識を有する方など)にお願いしております。
しかしながら、なかなか回答のつかない質問もあります。
投稿されてから2週間経っても回答がつかない質問に関しましては、職業などに関係なく、ご回答のご協力をお願いしたいと考えております。 -
白書の皆様におかれましては、貴重な時間を割き、子どもたちの質問に丁寧にお答えくださったり、叱咤激励してくださって誠に感謝しております。
このようなお願いをするのは大変恐縮なのですが、勇気を出してこのサイトに質問を投稿してくれた子ども達に、よりよい情報を提供したいと考える当サイトの運営ポリシーをご理解・ご了承いただけますと幸いです。
 小説の表現について
小説の表現について
[Q] はじめまして。私は小説家を目指していますが、そのことについて質問をさせていただきます。
私は他作品に感化されやすく、気に入ったフレーズが頭に残っていて、小説を書いている時、無意識にそのフレーズに似た表現を使ってしまうことがあります。
悪気はなくて、書いている時は無意識でも、それは著作権に関わってしまうことでしょうか。
小説は真似することから始める、といいますが、どこまで真似して使っていいのかよく分かりません。
よろしくお願いします。
あすかそうさん、コメントありがとうございました。
いままで文を書くとき、なにを伝えたいのか、ということは漠然としか考えていませんでしたが、あすかそうさんのおっしゃった通り、大切なことだったんですね。
文章に携わる職業の方に聞けて、ありがたいです・・・・。
読む人の心に響く小説を書けるようになるためにも、伝えたいテーマを念頭に置いて、ひたすら頑張っていきたいです。

こんにちは。
霧音さんの質問の回答は
ぶるまんさんの書かれている事で解決できるかと思いますが、
ひとつだけ、加えさせてもらいたいと考え
コメントさせていただきます。
私は小説ではなく、取材記事などを書く仕事をしてますが
小説も記事も「何を伝えたいのか?」が伝わる事が大切です。
もし、書かれた小説の全編にわたって、
感化された話のフレーズをつかいまくっていたら
真似と言われてしまうかもしれませんが
日常の会話の感覚で一言二言と出てくる分には
真似や似せているとは言われないでしょう。
今は、伝えたいスト−リーや小説を通して伝えたい事を
言葉に込めて書く事だけを意識してみてはどうでしょう。
その結果、霧音さんの作風が形成されていくと思いますよ。
お互い、言葉を大切にしつつ
読んでくださった方々に、伝わるものを
書いていきましょうね!
ぶるまんさん、回答ありがとうございました。
出版関係の方のご意見を聞けてとても嬉しかったです。
まずは自分の好きなように表現、との言葉に気持ちが楽になりました。
これから、自分の作風を出せるように精進を重ねていきたいと思います。
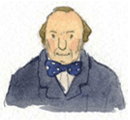
霧音さん。
改めて、他の作品で使われている表現を自分の作品で使ってよいかどうかについてお答えします。
他の作品からストーリーやアイデアを含めて表現を模倣、いわゆるパクることについてはもちろん問題がありますが、文体や表現を真似することは「著作権法的には」問題はありません。
仮に著作権侵害で訴えられ法廷で争うことによっても、現在の判例では侵害していると認められることはないでしょう。仮に侵害していると認められた場合、それは全く新しい判例になり出版界は大騒ぎになります。
ただし問題がないというのはあくまで「法律的には」の話であり、世間で盗作疑惑、パクり疑惑が出れば、作家、そして私ども出版社にとっても大きなイメージダウンになってしまいます。
特に最近はインターネットなどで作家に対して直接批判や中傷が浴びせられるため作家自身がそういった批判に耐えられないということもよくあります。
本来、作家の作品に他の作品の模倣ととられかねない表現がないかチェックするのは私ども編集者の仕事になります。ただ編集者もすべての作品と読み比べることは不可能です。この文章はこの作品のこの部分に影響を受けていると思うがこれは問題ないか、と編集者に自己申告していただけると助かります。
そしてよい作品の表現を真似ること自体は大いに推奨します。
もし気に入ったフレーズがあるのなら、それは是非使ってみてください。乱暴な言い方をするなら他の作品の作家の気持ちは考えるなくていいです。まずはあなたの気持ちを大切にしてください。
奇をてらってあなた自身の新しい表現をしなければいけないなどと考えないでください。小説は作家自身のものです。まずはあなたが好きなように表現すればよいのです。
著作権とかそういったことを気にせず、どんどん作品を書いてください。最初は真似になってしまうかもしれませんが何本も書くうちにあなた自身の作風も出てきます。
是非頑張ってください。
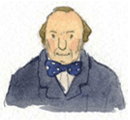
小説中の表現と著作権について余りに酷い回答がされているので筆を取りました。
> 基本的には、「創作的」な部分をまねるのは、すべて違法で、合法的にまねるには著作権所有者の許諾が必要ということになります。
この回答は酷い間違いです。
「創作的」部分ということになれば、例えば小説のアイデアも「創作的」なものになりますが、小説のアイデアを真似ることは著作権法上何ら問題がありません。
反対に、質問者のようにアイデアやストーリーは異なる小説の中で、表現方法や文体のみを真似ることも著作権法上何ら問題はありません。
少なくとも日本の著作権法では、アイデアと表現がセットになって著作権というものが発生します。その片方のみを模倣した場合はいわゆる著作権侵害にあたりません。
あきちゃんで~す氏はあたかも著作権についてよく知っているかのような口調ですが、これらのことは著作権法に関する基本的なことです。
著作権に関しては無知、むしろ間違った知識を本当であるかのごとく書き重ねるあたり無知より始末が悪いと言わざる得ません。
さらにもう1点、あきちゃんで~す氏の間違いを指摘しておきます。
> 数年前に、現役の大学生が「芥川賞」を取って大きな話題になりましたね。
> その方も、幼少の頃から「物書き」を意識していたそうです。
ここ数年では、現役大学生が芥川賞をとったという事実はありません。
現役大学生で受賞しているのは石原慎太郎氏、大江健三郎氏、村上龍氏、平野啓一郎氏、綿矢りさ氏の5名のみです。
仮に2004年の綿矢氏、1999年の平野氏を「最近」と無理に解釈したとしても、綿矢氏も平野氏も小説を書き始めたのは高校生からであり、「幼少」というのには当たりません。
ご自分の都合のいいように嘘を事実のように語られるのは、問題があります。
他のトピックでも氏の書き込みが問題になっているようですが、嘘の書き込みだけはやめていただきたい。

霧音さんへ
その通りと思います。
数年前に、現役の大学生が「芥川賞」を取って大きな話題になりましたね。
その方も、幼少の頃から「物書き」を意識していたそうです。
もちろん、「早く始める」ということ自体が、作家の価値を決めるものではないですが、「文豪」といわれる方は、みなさん学生時代から同人誌などで立派な作品を残していらっしゃいます。
霧音さんも、頑張って、良い作品をたくさん世に出して下さい。
丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
著作権のサイト、色々と参考になりました。
小説は真似することから始める、というのはどこかで耳にした言葉であって、「一億三千万人のための小説教室(岩波新書)」の存在自体、知りませんでした・・・。
まず、作者の気持ちを考えることが大切なんだなぁと思いました。
私なりに考えてみたところ、気に入ったフレーズを見つけてもそれを参考する程度にする、そして私は私の、全く別物の表現を作り出すことで初めて自分の表現になる、という結果に落ち着きました。

小説・イラスト・音楽などを、どの程度ならば、人の作品をまねても大丈夫なのかは、著作権法に具体的には書いてありませんのであしからず。
だから、著作権侵害をめぐって「裁判沙汰」になるのです。
基本的には、「創作的」な部分をまねるのは、すべて違法で、合法的にまねるには著作権所有者の許諾が必要ということになります。

>小説は真似することから始める、といいますが…
とありますが、この表現は、「一億三千万人のための小説教室(岩波新書)」から「引用」しましたか?
もし、そうなら、「真似をすることから始める」のであって、「真似をしているうちは、小説とはいわない」と思うのです。
字面だけで判断することは、まさに、「著作権法で保護しているところの作者の精神」に迫っていないのではないでしょうか?
もう一度、「小説を書く」ということの意義を考えてみて下さい。すてきなストーリーを思いつくことも大切ですが、物書きには、やはり「論理的思考能力」が強く要求されると思うので…

霧音さんへ
「著作権法」という法律によって、作者や所有者の権利が守られます。「著作権法」は、何条くらいあるかご存じですか?
…126条です。「附則」を入れるとさらに増えます。
ですから、この場で「こういう場合は○、これは×」とすべてを明確に答えることは「危険」です。知らないうちに法律に触れてしまう可能性があるからです。
私も大学生の時(法学部)、授業で著作権の単位を取ったのですが、「概論の講義」だけで一年かかりました。もちろん教授は、著作権を専門に研究している方でした。
ですから、細かい条文や規則を破ることを気にするより、「著作権保護の精神」を身につけてほしいと思います。
大事な考え方について、文化庁(著作権の担当官庁です)の青少年向けページをご紹介しますので、読んでみて下さい。そして、また質問があったら書き込んで下さい。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/hakase/hajimete_1/index.html
http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/index.html