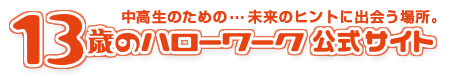HOME > もっと教えて!フォーラム > 人と植物の共存をサポート「花と緑」を扱う仕事 > 回答・コメントする(No.950)
もっと教えて!フォーラム
回答・コメントする(No.950)
-
いつも、子どもたちの疑問にお答えいただき誠にありがとうございます。
13hw編集部より、ご回答くださる際のポリシーに関するお願いです。
-
回答は、基本的には、その職業の方(または経験者、相応の知識を有する方など)にお願いしております。
しかしながら、なかなか回答のつかない質問もあります。
投稿されてから2週間経っても回答がつかない質問に関しましては、職業などに関係なく、ご回答のご協力をお願いしたいと考えております。 -
白書の皆様におかれましては、貴重な時間を割き、子どもたちの質問に丁寧にお答えくださったり、叱咤激励してくださって誠に感謝しております。
このようなお願いをするのは大変恐縮なのですが、勇気を出してこのサイトに質問を投稿してくれた子ども達に、よりよい情報を提供したいと考える当サイトの運営ポリシーをご理解・ご了承いただけますと幸いです。
 大規模農業について
大規模農業について
[Q] これからは個人の農家ではやっていけなくなり、仲間と手を組んで大規模で効率的な農業をしていかなくてはなりません。
農業もこれからは個人というよりは企業に近いイメージになると思いますが、そうなってきた場合、就職の一つの選択肢として魅力があると思いますか?

こんにちは。
こちらのサイトは「仕事に就くこと」について話す場所だと認識していますので、それを越えるテーマ(農業技術の是非その他)について、個々の意見を申し述べることは控えます。
このスレッドに関心を寄せた若い皆さんには、農業は魅力的なお仕事かもしれないよ、ということを申し上げたい。私の実家のすぐ横は典型的な近郊農業の畑地です。農家の皆さんのお仕事は、はたから見ていても大変そうですが、それでも皆さん充実した表情で仕事をされておられる。私自身も鍬ぐらいは扱えますので、ほんのさわりですが土に触れる喜びは知っています。
部外者から見ても、現在の農業を取り巻く環境は厳しいと思います。生産者・消費者ともに、理想と現実(あるいは許されること)のギャップが激しすぎることも一因でしょう。このギャップは、地球的規模での人の営みが生み出しているものであり、私達の存在そのものが大きく変わらない限り、永遠になくなりません。
そのギャップを解決することはできませんが、軽減する手段の一つとして、農業の大規模化・集団化、あるいは企業化という動きがあるのは、事実でしょう。その是非を論じるつもりは私にはありません。今後、農業の形態が多様化するのは間違いないでしょう。完全無農薬・有機生産による集団経営農場というのも、諸外国には例があります(経営は大変らしいですが)。先の書き込みで私が紹介した「野菜工場」は無農薬ではないはずですが、通常栽培よりかなり農薬使用量が少なくてすみます。
繰り返しになりますが、農業を志す方々にとって、こうした新しい形態の農業は、就農のハードルを低くするという意味でも、今後選択肢の一つになると思います。その中で農業としての魅力をどう見つけるかは、実際に就業される方が考えるテーマだと思います。

反発するわけではありませんが・・・・・・
遺伝子組み替え作物、食品照射(原子力の別利用)、クローン技術
、、、、ほかにもありますが。
農業の企業化は、上記の技術を肯定することになると思います。
効率化を求めることは確かに必要です。
しかし、現在の法制化の下では、アメリカ農業の二の舞になりかねないと思います。
私自信はEUの農業政策を参考にして日本農業の再生を計るべきと考えています。
最後に、「オーガニック」という言葉は何なのか?
「オーガニック生産者」は環境を大事にしながら農産物を作って消費者に供給しています。
硝酸態窒素・温暖化・水の問題まだまだありますが。
農業の企業化とは、これらの問題に対し密接に関係があることを
考えて欲しいです。

たかとんさんこんにちは。
私はとても魅力的だと思います。
現在、農業のあるかたが見直されてきていますよね。
以前は「きつい」との理由で農業を継ぐ若者が減ってはいましたが、
今は環境分野や教育分野などからも、農業の大切さ、素晴らしさがあげられています。
たとえば、農村留学などもそのうちのひとつですよね。
私は各学校で講師なども務めていますが、去年、私が契約している畑に生徒を連れて行ったことがあります。
みんなでサツマイモを掘りました。
土いじりなんてしたことのない子ばかりでしたが、本当に驚かされたのは、畑での役割を自分たちで率先して決め、
作業に取り組もうとする教室では見たことのない姿勢でした。
これは授業でもないし、仕事でもないのに、こんなに生き生きと逞しい生徒たちに出会えてよかったと
心から思いました。
また、私は学校ではエステ、いわゆる美容や癒しの分野について授業をしているのですが、最近よく耳にする言葉で
「ロハス」という言葉があります。
この「ロハス」の意味を空と自然の見えない教室で説明しても、生徒たちにはほとんど伝わりません。
でも、サツマイモ堀りを体験したことによってロハスを体感できました。
さらに、いろんなものを見て、触って、聴いて・・・農家の人たちとのコミュニケーションや、教えてくれた知識の中から、一所懸命に何かを五感で感じて、考えたようです。
もし、たかとんさんが農業を展開されたときは、是非、外へエネルギーを発信していただけると、次世代の子どもたちの農業に対する関心や感謝の心をずっと忘れずに、身近でとても大切なものとして捉えることができるのではないでしょうか?
私は、私たちの命を支える穀物や野菜だけではなく、人間や自然の在りかたの思想や哲学なども、農業から生まれるものとして大いにあると思っています。
ちなみに私が契約している畑は↓こちらです。
イベントなども多く、初めての体験をたくさんさせてくれます。
スタッフのかたたちも、レクリエーションの資格を持っていたりと個性的です。
私たちが遊びに行くとガイドさんをしてくれます。
http://www.morifarm.co.jp/

こんにちは。議論としてはひとまずおしまいのトピックかもしれませんが、就農者の外から見た感覚を述べておきます。
最近、ある製鉄メーカーの関連会社が新規事業として立ち上げた(ちょっと語弊がある表現ですが)野菜工場が、話題になったことがあります。製品としての野菜が一部の高級スーパーで販売されていますが、これがかなり美味しい。栄養価は路地物とまったく遜色ない。水洗不要なほど清潔なので、日持ちもいい。多少割高ですが、生産が安定しているので、季節や気候変動による価格の乱高下がない。また、意外と見逃しがちですが、土地の単位面積+消費資源あたりの生産性がかなり高い。もっとも、まったく土の香りのしない野菜には抵抗感を覚える、という方も少なくないでしょう。
これと同じレベルの生産を個人の農家の方が行うのは、(あくまでも部外者の視点ですが)ほとんど不可能だと思います。もちろん、努力を惜しまない方々がおられるのは嬉しいのですが、私達がその努力に報いるためには、の代価が必要=作物の価格が高くなります。また、残念ながらそうした形式の農業は生産性が低くなる傾向にあるため、それでなくても食料自給率の低い日本にとっては、かなり贅沢なものとなるでしょう。でも、やっぱり野菜は土の香りがしないと、と感じるのは、ごく自然なことだと思います。
他の産業以上に、農業においては品質と生産性・価格は強いトレードオフの関係にあります。ある程度の品質を維持しつつ、国(というより地球全体)としての緊急の課題である生産性の向上と価格の維持を図るためには、特に日本においてはある程度の農業の集約化、場合によっては企業化という流れは、不可避のように思われます。
その結果として、ある種サラリーマン的な就農者が誕生することが予想されますが、これはこれでかなり魅力的かもしれません。現在、素人が就農を志すのはなかなかハードルが高いことは、実際に就農されている方のほうがご存知だと思いますが、一方で、今は違う仕事をしているけど、農業に魅力を感じるという人々がたくさんいることも事実です。そんな方々にとって「サラリーマン的就農者」は、農業を志すチャンスになりうるのではないでしょうか。
一方で、例えば完全有機農業を実践される個人農家の方がいるのは、実にすばらしい。従来農法で安価な農作物を供給してくれる農家も絶対に欠かせない存在です。他の産業と同じように、農業でも様々な事業のあり方があっておかしくないと思います。
ただ、どれか一つに偏ると、たちまち食糧需給のバランスがおかしくなってしまう。互いに補完しながら、農業全体として社会を支えていただければ、消費する側としてはとてもありがたく思います。こうした仕組みの中に、将来企業的農業経営が加わることは、決して不自然ではないでしょう。そこに農業としての魅力をどう見出すかは、実勢に就職される方が判断すべきことだと感じます。

私は有機農業を実践していますが(HPみて頂くと分かりますが)農業の企業化に対して違和感を感じます。農業の基本は食べる人の健康を守る事が使命だと感じるからです。法人化して利潤追求に走るのは時代の流れだとは感じていますが、、、農業に興味を持ち実践するならば消費者との交流を大事にするべきだと思います。
特に次の時代を担う子供達の健康を担うことが一番大事なのでは。
国が法人化に対して補助金をだすのは単に外国との競争力を高めるためで食べる人の事はあまり考えてはいません。
とにもかくにも食べていただく人の声を聞いて
進んでいけば自分の先はおのずと見えてきます。
どうしても、市場の価格を基準にして作物を作り
それに合わせてコストを計算し生産すれば消費者に合ったニーズのものは作れないでしょう。(ですから、法人化という考え方になってしまう)
しかし、消費者の理解を得ながら生産していけば
本当に安全な欲するものを生産し喜んでもらえますょ。
:question:

従来の日本の農業は、個人若しくは家族単位の労働集約型の地味なイメージでした。
その地味なイメージの影響もあり若い世代からは敬遠されがちでした。
職場での出会いはいつも顔を合わしている家族というのは、若い世代のみならず
あまりにも刺激のないものです。
大規模農場(大規模農業)に移行していけば、他人との関わりの中での刺激もあり情報交換、技術・ノウハウ
等の向上にもプラスにはたらいて行くことでしょう。
ただ、経営面では税務面、利益配分等の問題も沢山あるので
「大規模農業」という前向きの発想でありながら、なかなか前へ進まない理由ではないのでしょうか?
私は是非やってみたい!
テレビで工場みたいなところで野菜を作っているのを見ました。
生産や品質が安定するそうです。
そういった感じでしょうか