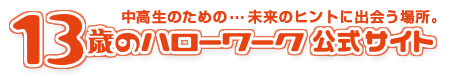公文書館専門職員(アーキビスト)
<< 編集部の職業解説 >>
国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書を公文書(アーカイブ)と言う。その中で、永久保存価値のある、法令の原本や条約、宣言、外交文書、政府関係者の報告書や伝達メモなどは、公文書館(文書館(もんじょかん)ともいう)で保管され、必要に応じて公開される。
博物館には学芸員(キュレーター)、図書館には司書(ライブラリアン)という専門職のスタッフがいるように、公文書館におけるそれがアーキビストである。主な仕事は、情報の査定、収集、整理、保管、管理で、扱う媒体は、書類をはじめ、写真、音声、ビデオ、手紙、デジタルデータなど多岐にわたる。
情報の種類・内容によっては、一般の人に広く知ってもらうために公開するが、そのときは、企画からプロモーション、新聞・テレビでの紹介まで対応することもある。
また、インターネットの普及により、オンライン上で閲覧するニーズが高まっており、情報をデジタル化するにあたり、インターネットの知識も要求されている。
イギリスのヒラリー・ジェンキソン氏は、1922年に著した『アーカイブ管理の手引き』で、アーキビストがやるべきことについて説いた。これが、専門職としてのアーキビスト誕生のきっかけといわれている。
さらに、1956年にT.R.シェレンバーグが著した『近代のアーカイブス』では、アーキビストの仕事の流れや、整理の仕方について詳述。これにより、その仕事内容がより明確になるなど、欧米においてはアーキビストを専門職ととらえ、認知されるようになった。
一方、日本ではまだまだ認知度が低く、多くの施設で、古文書や行政資料などの歴史資料を扱う専門の教育を受けていない司書や学芸員が行っているのが現状で、アーキビスト養成の基盤づくりが急務となっている。
アーキビストには、担当する分野に対する専門知識をはじめ、記録・管理・修復の知識と技術、さらに法的知識など、幅広い知識が要求される。
そのため、ほとんどのアーキビストが大学でアーカイブ学を学び、さらに大学院に進み、図書館学、図書館情報学、歴史学、政治学、法学、記録管理学、コンピュータ・サイエンス学などを修めている。
さまざまな大学で、アーキビストコースが開設されており、アーキビストについての知識を得ることができる。また、社会人向けの講座などもあるので、社会に出た後に興味を持った場合は、そのような講座を受講し、学ぶことができる。
この他、アーキビスト・サポート(ASJ)が定期的に「アーキビスト・カフェ」を開催している。アーキビストに関心のある人であれば誰でも参加できるので、そこで情報収集することもできる。
=> アーキビスト・サポート(ASJ)(http://www.ne.jp/asahi/archivists/support)
この職業解説について、感じたこと・思ったことなど自由に書き込んでね。
わからないこと・知りたいことは、働いている大人に聞いてみよう!
- 社会保険労務士
- 福祉施設栄養士
- 点字通訳者