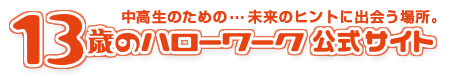小道具
<< 編集部の職業解説 >>
映画やテレビ、舞台で使う小物をそろえるのが、小道具の仕事である。そろえ方には、「借りる」「買う」「つくる」の3つの方法がある。たとえば、衣装や家具類などはメーカーやショップから借り、飲み物や食べ物などの消費するものは購入する。そして最終手段として、イメージするものがどうしても見つからない場合は、専門業者に依頼して作ってもらったり、あるいは自分で手づくりしたりする。
ドラマ、情報番組、バラエティーというように、内容に応じて必要なものをイメージし、限られた時間で必要なものを仕入れなければならない。それには、小物類に関する情報を豊富に持ち、てきぱきと行動することが肝要だ。
こうして集められた小物はあくまでも演出の一要素に過ぎないが、場面の雰囲気づくり、役者の個性の演出に重要な役割を担っている。
そろえた小物類によって、役者の嗜好や経済的背景だけでなく、生き様までも表現される。そのため、センスだけでなく、役を作り上げる緻密な計算が要求されるが、そこが小道具の腕の見せどころでもある。
時には、役者が身につけていた小物が脚光を浴び、巷で流行を巻き起こすこともある。そんなときは、小道具冥利に尽きるだろう。
また、経験を積み、実績を重ね、それなりの地位に就けば、番組の最後に名前が出ることも。それは、言い換えれば自分の仕事が認められている証でもあり、よりよい仕事をするモチベーションにもつながる。
小道具の仕事に就くのに、とくに高い学歴は求められていないため、高校卒業後、小道具の制作会社やリース会社に就職して現場で経験を積むのが、最短の道といえよう。
しっかり準備して就職したいのであれば、芸術系の大学・短大や、放送や映画関連の専門学校で、必要な知識および技術を身に付けることができる。
なお、募集は不定期かつ随時という会社が多いため、学校の就職相談窓口に聞くだけでなく、希望する会社のホームページをまめにチェックするか、直接電話やメールで問い合わせるのがよい。
日常にあふれている身の回りのものについて、つねに興味や関心を持ち、情報収集しておくことが大事である。
仕事のために「学ぶ」というよりも、興味があるから自然と目が行き、チェックして、自分の情報の引き出しにストックしているような人が、この仕事に向いているだろう。
【職業解説】美術・美術監督・デザイナー
【職業解説】舞台美術
【職業解説】大道具
【職業解説】小道具
この職業解説について、感じたこと・思ったことなど自由に書き込んでね。
わからないこと・知りたいことは、働いている大人に聞いてみよう!
- CMプロデューサー
- 放送記者
- CMプランナー