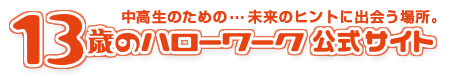HOME > もっと教えて!フォーラム > 今も未来も必須のインフラ「IT・Web」の仕事 > 回答・コメントする(No.12014)
もっと教えて!フォーラム
回答・コメントする(No.12014)
-
いつも、子どもたちの疑問にお答えいただき誠にありがとうございます。
13hw編集部より、ご回答くださる際のポリシーに関するお願いです。
-
回答は、基本的には、その職業の方(または経験者、相応の知識を有する方など)にお願いしております。
しかしながら、なかなか回答のつかない質問もあります。
投稿されてから2週間経っても回答がつかない質問に関しましては、職業などに関係なく、ご回答のご協力をお願いしたいと考えております。 -
白書の皆様におかれましては、貴重な時間を割き、子どもたちの質問に丁寧にお答えくださったり、叱咤激励してくださって誠に感謝しております。
このようなお願いをするのは大変恐縮なのですが、勇気を出してこのサイトに質問を投稿してくれた子ども達に、よりよい情報を提供したいと考える当サイトの運営ポリシーをご理解・ご了承いただけますと幸いです。
 「COBOL技術者が死滅していた」という妄言の意味、根拠は?
「COBOL技術者が死滅していた」という妄言の意味、根拠は?
[Q] またしてもこの「13歳のハローワーク」という「問題作」の中の記述について「これはどうしても自分の頭では理解のしようがない(したくもない)」という部分がありましたので、お分かりになる方がいたら是非ともお答えいただきたいです。
サイト上にも記載されていますが、伊藤譲一とかいうどこの馬の骨ともわからない山師がこんなこと↓を書いていました。
http://www.13hw.com/special/ps_02_02.html
2000年問題のときに、悲惨な出来事がありました。2000年問題で危険視されていた大昔のコンピュータには、COBOLというプログラム言語が使われているものがあって、それで困ったことに、COBOLというプログラムを書いていた人たちは、もう死んでいて、いないわけです。
これをみて私は本当に顎が外れそうになるぐらい開いた口が塞がらなくなったのですが、何を根拠にこんなフザケきったことを言ってるのでしょうか?
この「死んでいて、いないわけです」というのが文字通り「墓の中に入っていた」というのであれば、なにを根拠に言ってるんでしょうか???
COBOLという言語は少なくとも80年代まではよく使用されていた言語であり、今から数えてもせいぜい30年ぐらいしか経っていませんが、それを「書いていた人たち」が「もう死んでいて、いない」という証拠がどこにあるんでしょうか?????
「江戸時代に浮世絵を書いていた人たち」ならば戸籍という具体的証拠もあるし、いちいち調べなくとも「もう死んでいて、いない」のは100%当たり前と言えますが、この伊藤とかいう人は全COBOL技術者の戸籍情報でも握っているのでしょうか???????
少し検索をかけてみてもCOBOLが書ける(業務で使用している)ユーザなどすぐに出てくるし、wikipediaにも書いてありますが
http://ja.wikipedia.org/wiki/COBOL
この伊藤とかいう人は頭がおかしいのでしょうか????????
あるいは「引退するなり忘れるなりした技術者が多く、数が非常に足りてなかった」という意味をオーバーな表現で表したのかもしれませんが、それだったら死んでいない人を「もう死んでいて、いない」などと言うのはまさに侮辱的、不謹慎ではないでしょうか。
こんな事実誤認、侮辱、不謹慎な内容を平気な顔して「子供たちの未来のため」などと称して平気でタラシこむ「13歳のハローワーク」(およびそれを出した作者、出版社)というものは本当に酷いものだとしか言いようがありませんね。
もし私の認識が間違っているというのであればぜひとも「お分かりになる方」にご教授いただきたいのですが、いらっしゃいますかね??????

例えば、ラーメンを蕎麦屋さんが売り出すとします。
チャーシューを載せるのが当たり前かもしれませんが、
店によってはチャーシューは高いし、コストがかかるので載せないかもしれません。
お客さんが「チャーシュー入ってないじゃん!」と怒っても、チャーシューは店の方針があって載せれません。
それが、「13歳のハローワーク」みたいなもんです。
「伊藤穰一」という人はよく知らないですし、勝手にCOBOLのことを死んだプログラミング言語のように言ってるけど、
明らかに間違ってるのはネットで調べればわかる。
でも、「13歳のハローワーク」というラーメンでは「伊藤穰一」という人が言ってることが正しいことになっているのです。
2003年に出版したから、もう、11年前の本です。
ツッコミどころ満載の発言で、当時問題となったようですが、ネットの「13歳のハローワーク」でも改訂されていないところを見ると、
そのラーメンの味は変えないでいたいという思いがあるのかもしれません。
「13歳のハローワーク」は、ほかにも、プログラマを「夢のない職業」と書いたりしていて、発売当初から各会派で問題になっていたんです。
確かに、金メダルとるような職業は素晴らしい職業で、夢があってオススメしたい職業かもしれません。
でも、そんなのに就ける人なんてごくごくわずか。1000人いたら3人くらいしか成功してなくて、日本では戦争より酷い年間3万人の自殺者をだし
ている。
例えば、金に困ったとして、一攫千金を狙って「宝くじ」なんてものを買ったとしても、一等を取れるのは「1/1000万」(いっせんんまんぶんの
いち)。たまに、何を考えたのか、本当に金に困って、有り金全部投入して、宝くじを買い、当たらなくて死ぬ人もいるんですよ。
正直いいますが、COBOLを使うプログラマなんて、つまんなくてやりたくない人が沢山いて、「外注費、一人あたま1000万円くらいとれる」から、
強制的に仕事させられているだけです。
一人、1000万円下請け会社に支払われるのに、そのプログラミングをしている人の給料は350~400万円程度です。
COBOLに関してツッコムのであれば、「13歳のハローワーク」のメールアドレスに直接直談判するといいでしょう。
-------------------
Eメール : info@13hw.com
(株式会社トップアスリート内)
TEL : 03-6416-4547
FAX : 03-6416-4541
-------------------
貴方の場合、気概がありそうなので頑張ってその「伊藤穰一」という人が言ってることを「間違いだ!」と説得し、11年間、COBOLが死んだ言語に
なっていたことを覆すといいでしょう。
ただ、「13歳のハローワーク」の編集者がそれを受け入れるかどうかはわかりません。
いろいろ大人の事情が絡むでしょう。
「伊藤穰一」という方に、「13歳のハローワーク」では、いくらかのお金を出してコメントをもらっているはずですし、「それが無駄で、間違え
てることだった」と認めさせるのはまず無理だろうとは思います。
社会にでると分かるのですが、「約2年間」は苦しみます。
「石の上にも3年」と言いますが、3年目あたりになると、「業界の裏」、「会社の裏」などが分かってきて、人によっては「その汚い部分」を見
て辞める人も多いです。
「13歳のハローワーク」の書物を作るのに、2年か3年はかかっているでしょう。
一部、その業界からしたら納得いかない部分があったとして、苦情が来たくらいで、簡単に認めて改訂をするわけないじゃないですか。
「13歳のハローワーク」の改訂版がいつでるかはわかりません。
というか「13歳のハローワーク」自体、問題作なんです。
菓子職人やらパン屋やりたいと、警察官やら検事やら、なんか良さげなことを書いて、普通なれそうもないことをいいことだと書いて、
現実の厳しさを教えない。
確かに、「13歳のハローワーク」という本の特性上、致し方ない部分があるのかもしれません。
だって、13歳の子供に向けて書いている本ですよ。
大人がみたら、「そうじゃない」ってのは大量にあるんです。
今は、即戦力を取る動きがあり、1年目からバリバリやらされる場合も出てきました。
でも、1年目はお試し期間です。
「13歳のハローワーク」では、夢を見させすぎなのです。
どういう職業があるのかまでは解説するのは重要でいいことなのかもしれませんが、全員が全員希望の職種に就けて「幸せ」になれるかはわかり
ません。
まえ、回答したときには、「パン焼くからヨーロッパ行きたい」という質問者がいて、流石にやめろとは言いましたよ。
あなたの場合、自力でネットから情報も引き出せるようですので、今回の件は、2chに記事が残っているかもしれません。
PG、SEの論争については以下を参照
http://pc3.l2ch.net/test/read.cgi/prog/1076298046/
頑張って、13歳のハローワークに一雨ふらせてみてくださ。
以上

と書いてるのですが、相当昔に話題になったことなので、今、ほじくり返す段階にはないかと思います。
回答を2回書き直して、いま3回目を書いています。
貴方は、私のアンチだろうけど、それはそれ。
COBOLが使われているのは事実だし、「13歳のハローワーク」自体に問題があることもわかっています。
中学生の貴方には分らないことかもしれませんが、
どんなに正しいことでも、「ある人が白と言ったのなら」白である。
という場合も世の中にはあります。

ん~。いろいろ考えてみたんだけど、Wikipediaに載ってるとおりです。
▼▼▼▼▼
2003年出版の書籍『13歳のハローワーク』(村上龍)では、起業家である伊藤穰一の発言として「COBOLは過去の言語で、2000年問題にまつわる不具
合を修正できるプログラマは皆死んでしまった」という趣旨の記載がされ[8]話題となった[要出典]。また1990年代の日本のダウンサイジング全盛
期には、マスコミなどで「日本のメガバンクや官公庁は前時代のCOBOLを使っているから効率が悪い」との論調が多く見られた。しかし現実には
2012年現在でも、CやJavaと並び、COBOLは多数の企業・組織で使われ続けている。特にライフラインを支えるような重要なシステムでは、基盤と
なる部分は、現在でもCOBOLで開発や拡張が行われている事例が多い。
▲▲▲▲▲