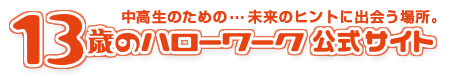HOME > 特集記事 > P.S.明日のための予習 13歳が20歳になるころには? > IT[Information Technology]
[INDEX]
- 1. はじめに(コンピュータの誕生)
-
2. Q&A:ITの現状と可能性(伊藤譲一×村上龍)
- 2-1 ITの仕事の未来像
- 2-2 テレビを見る人、作る人、分解する人
- 2-3 ウェブデザイナー不要の時代
- 2-4 植え過ぎた杉の木とSE
- 2-5 ITはバリアを乗り越える
- 3. Q&A:インターネットビジネスで成功するには?(高島宏平×村上龍)
- 4. おわりに(ITに希望はあるのか?)
2. Q&A:ITの現状と可能性(伊藤譲一×村上龍)
伊藤 穣一(いとう じょういち)
1966年生まれ。株式会社ネオテニー代表取締役社長で、日本におけるインターネット分野の指導的なビジョナリストで起業家。今までに、(株)インフォシーク、エコシスなど6社を設立。頻繁に政府顧問をつとめており、長期にわたるインターネット分野への貢献により、郵政大臣賞を受賞。米タイム誌において「サイバー・エリート」、米ビジネス・ウィーク誌において「日本のネット・ビルダー」、また技術分野において世界でもっとも影響力のある50人のうちの1人として紹介される。著書に『コンピュータ起業家』(実業之日本社)、『デジタル・キャッシュ』(共著、ダイヤモンド社)など。
Q:ITに関連する仕事について、13歳の子どもたちに、どう説明すればいいでしょうか?

【伊藤】電気にたとえるとわかりやすいかもしれません。電気に関連する仕事には、電力会社とか家電メーカーがあります。電気エネルギーや電気製品を使って仕事をする人もたくさんいます。たとえばデザイナーやミュージシャンも、照明器具や電気楽器を使います。そうやってできた作品を売るのが仕事という人もいる。そうやって、電気を供給したり、電気製品を作ったり、その製品を使って仕事をしたり作品を作ったり、できた作品を売ったり、いろいろな職種の人がいるわけですが、それらをひっくるめて、電気に関連する仕事、とはいわないですよね。
それなのに、ITの場合、それらを全部ひっくるめて、IT関連の仕事、になっている気がします。しかし、そういった状況は、今の13歳が大人になるまでには相当変わっていると思います。世の中のほとんどの職業で、ITが使われるようになるだろうから、ある種の勉強はしなければならない。ただいわゆるIT屋さんの仕事は、マニアックで地味な仕事になっていくと思います。
【伊藤】SEとかプログラマーはその代表かもしれないですね。たとえば、折り込み広告会社がオリコムという広告代理店になったり、鉱山会社が日立製作所になっていったように、IT企業といわれているものが、違う方向に向かう可能性があります。
たとえば、今、インターネット用電話回線をほとんど独占している電話会社は、ただの土管屋さんになるかもしれない。今、NTT(※3)が持っているもので重要なのは、実は、電信柱と土管だけなんです。だから10年後には、NTTは電信柱と土管の会社になっている、とかね。SEは、たとえば道路に立っている標識とか看板を描く人、みたいになっていくかもしれません。標識でも、看板でも、今はどんどん自動化されて、実際に標識を作ったり看板を書いたりする仕事はあまり必要なくなっているでしょう?
いまだに油絵や彫刻は作られていますが、芸術家のような仕事は、1000年単位で変わらない。でも、ITは毎年変わっていく。たとえば、ホームページをつくる巨大なシステムに、コンテンツ・マネジメント・システム(※4)というのがある。それは何千万、何億とかけて、何十人のSEでやっていたものなんだけど、同じことが、ウェブログ(※5)のソフトで、簡単にできるようになる。そうすると、SEという業種、それを抱える業界が、丸ごと吹っ飛んで、消えてなくなるかもしれない。新しい技術が出てくると、何万人という単位で雇用が消える、ITというのは、そんなことが実際に起こる業界なんです。
※1:SE(システム・エンジニア)
ユーザーの要望に応じてコンピュータシステムを設計士、仕様書にまとめるのが仕事だが、その関わる分野や仕事内容は顧客の業務や要求によっても変わってくる。企業などの組織が新たにシステムを導入しようとする場合、通常は営業職がその仕事を受注し、SEが設計し、それに基づいてプログラマーが作成していくのが基本となる。だがたとえば営業職が技術的な問題に対応できなければ、直接顧客とやりとりをすることになるし、逆に客に提案をするような場合もある。また開発チームのリーダーとして、プログラマーなどほかのスタッフをマネジメントしなければならないこともある。
コンピュータやその周辺機器について詳しいのはもちろんだが、事務や経営を含めて、客の求めに応じることができるだけの一定の知識が必要になる。SEには、ユーザー側の企業などにいてコンピュータ技術を学んでなる場合と、プログラマーなどコンピュータの専門技術者が実績を積んでなる場合がある。特に必要な資格はないが、経済産業省の実施する情報処理技術者試験などは、 SEとしての能力を見る目安のひとつにはなる。
※2:プログラマー
コンピュータが情報を処理する手順は、C言語やJAVA、Basicといったプログラム言語と呼ばれる専門の言語によって書き込まれる。プログラマーはSEが作った設計仕様書に応じて、プログラム言語を使ってプログラムを作成していく。ひとつのシステムを構築するためには膨大な数のプログラマーが関わることもある。プログラマーになるために特に必要な資格や条件はない。専門学校などでコンピュータについて勉強をしてから進む人も多いが、必須知識であるプログラム言語の習得を含めて、企業内である程度の訓練を受けることでも十分対応できるようになる。ある程度経験を積むとともに、たとえば客の業務などにも詳しくなることで、SEにステップアップすることが可能になる。
※3:NTT
日本電信電話株式会社。1985年、それまで日本の電話機を独占していた旧日本電信電話公社が民営化されて設立。その後再編され、持ち株会社のもと、東西のNTT、NTTドコモ、NTTコミュニケーションズなどに分割された。現在も日本で唯一全国の電話網を保有している。
※4:コンテンツ・マネジメント・システム
テキストや画像、音声などで表現された情報のことをコンテンツという。たとえばホームページを作成するためにはこうしたコンテンツが不可欠だが、コンテンツ・マネジメント・システムは、コンテンツの収集、作成、配信などを一貫してサポートするためのシステムで、主に大手IT企業が提供している。
※5:ウェブログ
ウェブページの形式のひとつで、個人の意見などを発表しあうのに適している。見た目はいわゆるテキスト系サイトに近いが、ウェブログのシステムを使うことにより、編集などの作業の多くが自動化され、操作が容易になる。アメリカでは個人が発信するジャーナリスティックなサイトが急増、コミュニティー形成の手段としても注目されている。
【伊藤】ハードウェアとソフトウェアも混ざってきています。僕は、後数年で、家電がインターネットのメインのインターフェイス(※8)になっていくと思います。ゲーム機や携帯電話、テレビ、デジカメがネットのツールになって、パソコンを使うのは、本当に必要とする人、本当にやりたい人だけになるでしょう。たとえば電気でいうと、家電を作っているメーカーは、ITに置き換えると、ハードやソフトを作っている会社や人ということになる。その家電製品を使って音楽を作っている人が、コンピュータを使いこなして仕事をしている人。その音楽を聴くのが消費者ということになるんだけど、僕は、さらに、音楽を作る人と、消費者というのも、しだいに境界が曖昧になっていくと思う。
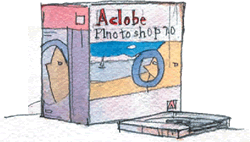
ただ、コアなIT業界は、そういった一般的なメーカーやユーザーから離れたところに、マニアックな形で残る。テレビにたとえると、テレビをバラバラに分解して、部品をいじったり、もう一度組み立てたりするのが好きな人って、数は相当少ないだろうけど、今だっているでしょう?
それで、テレビの番組を企画したり制作したりする人は、テレビを分解する人より多い。テレビを見る人は、分解する人より、番組を作る人よりもっと多い。それと同じで、コンピュータをいじるのが好きな人は、ハードやソフトを勉強して、コアなIT業界へ進めばいいけど、テレビを見るのが好きだというような人、つまりインターネットを楽しみたいという人は、コンピュータのハードやソフトを作る必要はない。そして、テレビにたとえると、テレビの番組を企画・制作したいというような人、つまりITを使ってクリエイティブな仕事をしたい人や、それとメディア関係の人は、ITのユーザーとしてプロにならなければいけない。いろいろと新しく次々に出てくるコンピュータやインターネットのツールを使いこなせるようになるための勉強をする必要がある。
※6:ハードウェア
キーボードやディスプレイ画面、プリンターなど、コンピュータ本体や周辺機器、関連機器のこと。これらを開発しているのはコンピュータメーカーをはじめ、半導体、家電、光学器械、精密機械などのメーカーが中心。携帯電話やデジカメなど、新しい製品が開発されるのとともに、ハードウェアの意味する範囲も広がる。今後の主戦場は、コンピュータと家電が融合した情報家電の分野ともいわれている。
※7:ソフトウェア
コンピュータを有効に動かすための手法、技術などの総称。プログラムはソフトウェアのひとつだが、プログラムそのものを指してソフトウェアということもある。産業としてソフトウェアを見ると、ハードウェアに比べて設備投資を必要とせず、その代わり人的資源に頼る部分が大きい。またソフトウェア産業は、主として一般ユーザーに向けた開発製造型のソフトウェアと、主として個々の企業を対象とした受注型のソフトウェアに大別される。アメリカでは前者が、日本では後者が主流だといわれ、受注型ソフトウェア開発の場合はサービス業的側面が強くなる。
※8:インターフェイス
異なる性質のものを結びつけることやその境界線という意味。ITの世界で使われるときには、異なる装置どうしを接続するための仲介の装置、特にコンピュータと人間との接点となる装置のことを指す。
Q:今、インターネットビジネス(※9)と呼ばれているのは、おもに、酒屋がインターネットでワインを売る、みたいなことです。そして、そのためのホームページのデザインや、決済システムのプログラミングを行うSEやウェブデザイナー(※10)が代表的な職種になっています。インターネットビジネスも、これから変わっていきますか?
【伊藤】酒屋がワインをインターネットで売るような場合ですが、今でも、楽天(※11)などを利用すれば、登録するだけでいいので、エンジニアは要らないんですよ。村上さんは、自分が作った本を1冊ずつ本屋さんに届けるということはしないでしょう。それと同じで、インターネットビジネスというのは、まだ宅配便がないころの物流のようなものだと考えればいいんです。列車やトラックや車を持っている会社や人が、荷物を預かって、1個いくらで、届けていたわけですが、宅配便ができると、そんな業種は不要になるでしょう。
Q:一般的な紙媒体のデザイナーはインターネットのHTML(※12)が書けないという状況では、ウェブデザイナーが特別の職業として成り立つ。でも、誰にでもウェブデザインができるようになると、専門的な知識や技術が不要になり、単にデザインの才能があるかないかという問題になると、そういうことですか?
【伊藤】ウェブログというソフトを使えば、HTMLなんて使わずにホームページのデザインができるようになります。今後、インターネットに関わる職業は、テンプレート(※13)を作って客を囲い込む方向に行くとか、ブラウザ(※14)のデザインだけを考えるとか、いくつかのパターンに分かれていく。ただし、ブラウザのデザインだけを考える仕事といっても、ブラウザの色合いをどうするか、文字フォント(※15)をどうするか、みたいなことは、HTMLを知らない一般の紙媒体のグラフィックデザイナーでも簡単にできるようになります。
Q:ホームページ制作会社(※16)も要らなくなるのでしょうか?
【伊藤】アマゾン(※17)のシステムを立ち上げるときのように、巨大なシステムを作る、ホームページを何万ページも作るというときには、必要といえば必要だけど、ただし、その仕事というのは、テンプレートをデザインする人と、ホームページの文章を書く人、1日に何百万件もあるアクセスを管理する人と、おおまかに、3つぐらいに分けられる。それらの仕事を分散させて、別個にアウトソーシング(外注)するか、自分のところでやってしまえば、制作会社に頼む必要はなくなるでしょう。
※9:インターネットビジネス
きちんとした定義は確立されていないが、インターネットを用いることにより、時間や場所、コストを効率化して商品やサービスを提供するビジネス全般を指す。インターネットを通じてさまざまなモノを販売する事業をはじめ、金融、レジャー、各種のコンテンツ産業からオークションやメールマガジンの発行まで、さまざまな分野に及ぶ。かつてはインターネットビジネス自体がひとつの産業としてくくられることもあったが、ビジネスの1つの形態として定着しつつある。多くの分野では参入が容易になったぶん、競争は激しくなっている。
※10:ウェブデザイナー
顧客の求めに応じて、そのイメージ通りにホームページをデザインする。文字や写真、イラストなど、基本となる素材は紙媒体の場合と同じだが、各種のソフトを使いこなせることとともに、利用者がアクセスしやすい工夫や、データ容量があまり重くならないようにする技術などが求められる。ただしソフトの普及で一般の人にも簡単にデザインができるようになるにつれ、より高度なデザイン力と技術力が求められるようになってきた。
※11:楽天
楽天市場。97年にスタートしたインターネットモール(インターネット上に設置された仮想の商店街)。次々と専門店街を立ち上げるなどして人気を集め、日本では最大の出店数、来客数を誇る。
※12:HTML
ネットワーク上にあるさまざまな情報を、誰もがアクセスできるように公開したシステムにワールド・ワイド・ウェブ(WWW)がある。HTMLは、このWWWで扱われる情報を表現するための一種の言語のようなもの。文字だけでなく、音声や画像を組み込むことができるとともに、ほかの情報へのリンクが容易なため、インターネットの普及とともに広まった。
※13:テンプレート
アプリケーションソフトに付属するサンプル文書のこと。文書の種類に応じた形式でつくられており、文書作成に利用できる。
※14:ブラウザ
「インターネット・エクスプローラー」のような、WWWなどのサイトを閲覧、利用するためのソフトウェア。
※15:文字フォント
ディスプレイ画面上における明朝体、ゴシック体といった文字の書体。
※16:ホームページ制作会社
ホームページのデザインからはじまり、制作全般、運営、管理などを行う。発注先の多くは企業であり、ビジネスのためにホームページを公開する。製作会社はこうした顧客のニーズに合ったホームページを制作する必要がある。製作会社には、デザインや広告、印刷、コンピュータシステムなど、もともとほかの事業をしていてこの分野に進出したところと、ウェブだけを専門に生まれたところがある。前者の場合はコンテンツ制作や広告、社内システムの構築など、本来の事業と関連する分野で強みを見せることも多い。後者の場合も、ほんの数人で地域に根ざした活動をしているところから、企業のプロモーションやシステム構築などにもトータルに関わっていくところまで、さまざまな製作会社がある。
※17:アマゾン
アマゾンドットコム。95年、アメリカ・シアトルでスタートしたオンライン書店。その後は書籍以外の商品も取り扱うようになり成長した。世界最大のデータベースを持つ。
Q:今、SEになろうかなと考えている13歳に、何かアドバイスがありますか?
【伊藤】プログラム技術に興味があるんだったら、勉強すべきだけど、SEというのは、電卓が普及する以前の、そろばんのプロ、みたいなものです。ソフトが一変すると、それ以前のプログラム技術はゴミと化す、みたいなことがよく起こります。
プログラムが書けるというのは、体力とか、腕力に似ています。ほかには何もできなくても、プログラムさえ書ければ、とりあえず今は仕事はあります。しかし、今でもすでに、ほとんどのSEの仕事というのは、一日中同じ形に積み木を積み重ねているような単純労働です。もちろんそれとは別に、天才的なSEもいるわけですが、それは体力、腕力でいえばオリンピック選手になるのと同じぐらいの才能と力が必要なんです。
Q:日本政府は、かつてITで数十万人の雇用を創出するなんて言っていましたが、そんなことが可能なんですか?
【伊藤】たとえばSEという職業ですが、新しい技術が次々と生まれて、ソフトも変化していくなかで、わずかな例外を除いて、最終的に不要になるかもしれません。それがわかっていながら、SEをどんどん育てている、というようなところがあります。昔、林業の国家プロジェクトとして、杉の木をたくさん植えたのと似ているんじゃないかな。あのころ植えられた杉の木は、間伐や雑草取りなど、手入れが大変で、結局、切って売ってもコストに合わないから、今も大量に残っていて、密集しすぎて山林がダメになるのではないかと危惧されています。ITも、労働コストの面で、中国やインドに、もうかなわないわけです。だから、SEのような単純労働ではなく、本当はもっとクリエイティブな部分に、子どもや若者の興味を向けるようにしないといけないと思います。
Q:結局、ITが普及すればするほど、ITに詳しい人より、もっと一般的に、創造性や独創性のある人や、コミュニケーションスキルのある人のほうが、有利になっていくということですか?

【伊藤】最初にいったように、これからの社会では、どんな職業や仕事にも、より深くITが関わるようになります。だから、勉強はしなければならない。ただ、その勉強というのは、まずコンピュータに接触することから始まるとしても、たとえば外国人とインターネットで友だちになれるとか、チャット(※18)やネットコミュニティーに入ることで、何が自分に向いているか、どうすれば自信が生まれるのか考えるとか、そういうことだと思う。
このエピソードは、いろいろなところで報道されたけど、サラム・パックスという20代の建築家がバグダッドにいて、彼は戦争の前からウェブログをやっていて、インターネットでレポートを発信していました。戦争が近づくと、しだいにレポートの内容がシリアスになってきて、世界中の人がそれを読むようになった。戦争中に電源や回線が落ちて、ネットで友だちになったイスラエルの女の子に、ディスクを送って、アップしてもらうようなこともあったけど、結局イギリスの新聞社が彼をコラムニストとして雇い、今では連載を持っている。彼が成功したのは、ひとつは英語ができたこと。インターネットを使って自分の声を伝えようとしたこと、その内容が面白かったこと、などいくつかの理由が考えられます。それで彼は数カ月で世界的なコラムニストになっていった。僕は、結局ITというのは、言葉のバリア(障壁)、国境のバリア、階級のバリア、文化のバリア、民族や宗教のバリアなど、さまざまなバリアを乗り越えていく手段だと思っています。
※18:チャット
コンピュータネットワークを通じて、リアルタイムに文字ベースの会話を行うシステム。1対1で行うものや、同時に多人数が参加して行うものがある。パソコン通信サービスの機能の一つとして提供されてきたが、現在ではIRC(Internet Relay Chat)などのようにインターネットを通じて利用できるものもある。また、なかにはビデオや音声でチャットができるサービスもある。
P.S.明日のための学習
13歳が20歳になるころには
-
いろいろな働き方の選択
-
IT[INformation Technology]
-
環境-21世紀のビッグビジネス
-
バイオは夢のビジネスか(commiong soon...)