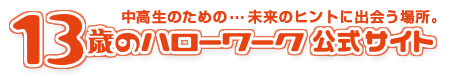HOME > 特集記事 > P.S.明日のための予習 13歳が20歳になるころには? > IT[Information Technology]
[INDEX]
- 1. はじめに(コンピュータの誕生)
- 2. Q&A:ITの現状と可能性(伊藤譲一×村上龍)
-
3. Q&A:インターネットビジネスで成功するには?(高島宏平×村上龍)
- 3-1 食品流通とIT
- 3-2 本質的な問い「ニーズはあるのか?」
- 3-3 複合的な情報ネットワーク
- 3-4 「安全・安心」の次のステップ
- 4. おわりに(ITに希望はあるのか?)
3. Q&A:インターネットビジネスで成功するには?(高島宏平×村上龍)
高島 宏平(たかしま こうへい)
1973年生まれ。オイシックス株式会社CEO。大学院時代に、オイシックスの前身となる有限会社コーヘイを立ち上げている。卒業後、マッキンゼー日本支社に入社し、Eコマースグループのコアメンバーの1人として、Eコマース実行の組織体制や、ベンチャーと大企業の共存によるEアライアンスの構築について取り組む。2000年に同社を退社し、「一般のご家庭での豊かな食生活の実現」を企業理念とし、食材販売・食生活サポートを行うオイシックス株式会社を設立。生産者の論理ではなくお客さまの視点に立った便利なサービスを推進している。
Q:安全であるとか、健康によいなど付加価値が高い食品のインターネット販売会社オイシックスを、始めた経緯を教えてください。
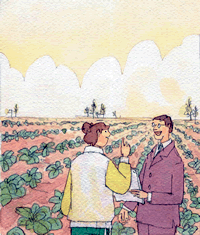
【高島】ビジネスとしてのチャンスと、個人としての思いと、両方がありました。前の職場は、マッキンゼーという外資系のコンサルティング会社で、食とは直接仕事上の接点がなく、そこで、数年前インターネットがようやく始まりつつあった時代に、ちょうどインターネットを使ったいろいろなビジネスをお手伝いしていました。それで、ビジネスとして、自分でも、何かを、ITというものにはめてみたいなと思いました。それでどういう業界が面白いかなと考えたときに、日本の食品流通というのはITとの親和性が高いんじゃないかと思ったのです。
まず1つには、日本の食品流通業界というのは、中間業者が多いということがあります。生産から消費という順路でたどると、まず農家があって、地方の農協があって、大きな農協があって、中卸があって、八百屋があって、我々消費者がいる。さらにもう1つ問屋が入る場合もあって、生産から消費までがすごく長い。当時は「中抜き」という言葉がよく使われていましたが、それをITを使うことによって行うことのインパクトは、結構大きいんじゃないかと思いました。
もうひとつ、当時から「からだにいい食べ物はなんだ?」というようなことを取り上げるテレビ番組は多くあったのですが、本当は「からだにいい」というのは人によって全然違うと思ったのです。ファイナンシャルプランナーという職業がありますが、何がからだにいいかを一概にはいいにくいなかで、同様にフードプランナーのようなものがあるといいんじゃないか、という発想がありました。ただ実際にひとりひとりに栄養士をつけていくのは難しいので、ITを使うことによって擬似的に自分の栄養や食生活を見てくれる状況が作れるのではないか。そこでもインターネットが力になります。仕入れ側との間でも有効だし、お客さんとの接点という意味でも活用できる。またそういうことをやっている人もいないようだから、ではやってみようかなと思ったのがひとつのきっかけでした。
Q:食品を売る、ということが最初にあったわけではなくて、何かインターネットと結びつけられるものはないか、というアプローチだったわけですね?
【高島】どちらかというとそうです。昔から野菜が好きで始めた、というタイプではないです。
Q:前に勤められていたマッキンゼーではどういう仕事をされていたんですか?
【高島】おもに、インターネットを使ったもので、ビジネスモデルを作って、場合によっては外国の会社を持ってきたり、ベンチャーと大企業をつないだり、そういう仕事をしていました。
Q:オイシックスの、インターネット販売の、ホームページにおける商品紹介や決済のシステムは独自に開発したのですか?
【高島】そうです。結構かかりましたが、たぶん普通の会社がやるときの10分の1ぐらいで済んでいると思います。うちは人にお金をかけて、設備にはかけないんです。いつも一緒に仕事をしている優秀なエンジニアがいますから、ソフトもハードも見積もりが一桁違うなと、すぐにわかるんです。
Q:ちょっと食品の話から離れますが、IT業界、あるいは、今のSEやプログラマーのようないわゆる「IT屋」の仕事というのは、5年後、10年後にはどうなっているとお考えですか?
【高島】今の仕事の立場でITについて感じるのは、やはりアメリカなどでは、インターネットというのはインフラです。電話やFAXみたいなもの、というイメージなんです。本来はそれを使って何をやりたいのかというのが一番最初にあって、やりたい人たちをサポートするために、SEやプログラマーがどんどん出てくる、という順番だと思うんです。実際アメリカでネット産業が盛り上がっていったのは、まず最初に「これをやりたい」「あれをやりたい」という人がいっぱい出てきたからです。ゴールドラッシュの後に、結果的にジーンズ屋さんが生まれていったのと同じような感じだったのですが、日本の場合は、「自分はこれをやりたい」という具体的なプランを持っている人は少なくて、ジーンズを売りたいという人ばかりがすごく増えたという印象があります。だから人数的なバランスという意味では、ある職種は供給過多になるという感じがあるのでしょう。もっと「自分はこれをやりたい」という人が出てきて、その結果SEを増やさないといけないねというようになっていくと、面白くなっていくかなという気がします。
Q:オイシックスは、食品ビジネスでもあり、ITビジネス、インターネットビジネスでもあります。IT、インターネットをツールとしてうまく利用しています。これからのインターネットビジネスを象徴しているような気がしますが、いかがですか?
【高島】ITにしても、インターネットにしても、いかにうまく活用するか、だと思います。現段階では日本の場合、電話線を引く人ばかりが多くて、電話を使う人がなかなかいないというような印象がありますから。
Q:インターネット販売だと、確かにムダな流通経路を省くことができますが、食品は生産地もさまざまだし、品質のチェックも必要で、生産物の調達もなかなか面倒だと思うのですが、ビジネスとして成立すると判断したポイントは何だったのでしょうか?
【高島】最初に一番考えたのは、調達ができるかということよりも、ニーズがあるかというところです。「何を食べたらいいかわからない」世の中だといわれています。食品に対して私も普通の20代の男性レベルの関心しかなかったのですが、そんな私でも、スーパーやコンビニで買ったものを食べて、「きっとからだに悪いんだろうな」と思っていた。すごくおかしな状況だとは思っていたんです。あまりにも不思議な状況なので、いつかは是正されることになるんじゃないか、それなら自分たちもその流れに参加しよう、と思ったわけです。自分ではそう考えるんだけれども、ではもっと食に関心が高い方はどうだろう、ということで、ヒヤリングをしたんです。特に女性ですね。結婚されたばかりだとか、妊娠されているとか、主婦の方に話を聞きました。
聞いてみると、やはりみんな漠然とした不安は持っている。かといって、当時から自然食通販みたいなものはあったのですが、それは何が入っているのかわからない野菜のセットが毎週3000円分届くものだったり、ちょっとハードルが高かった。当たり前の要求なのですが、安全でおいしいものを苦労せずに買いたいという欲求が非常に強い、というのを感じました。ニーズがあるとわかった後は、そういった生産物をどうやって購入するか、ということですね。やはり調達するのは最初はすごく大変でした。農家さんの反応は「インターネット? そんなのはやめておけ」みたいな感じで、全然信用してくれない。それが続いて、ようやく「おまえら変わっているから、やってやるか」という農家が、3軒、4軒と見つかっていった。
Q:野菜でスタートをしたというのは、どうしてですか。
【高島】主婦へのヒアリングなどでも、安全性とか味の違いについての意見は、野菜が一番多かったんです。あるいは肉、加工乳製品です。まずそこでやっていこうというのと、もうひとつは物流とか調達を考えると、野菜は一番ハードルが高いんです。そこからまず押さえてやっていこうというのがありました。
Q:どの農家が作っている野菜がおいしくて、かつ安全なのかというのは、ほかの情報に頼ることなく、オイシックス自身で調べていくわけですよね?
【高島】そうですね。当然、安全基準みたいなものは絶対評価としてありますので、このラインを超えていないとだめ、というのはあります。農家さんと話をしていると、たとえば「こういう病気が出たときにどうしていますか?」と聞くと、農薬を使ってしまっているとか、そういう話が出てくるんです。またうちには栽培管理表というのがあって、かなり細かく栽培の履歴を記入してもらっているんです。それを書けないのなら一切やらない、ということにしているので、そこで脱落してしまうケースもあります。最近は売り込みを多く頂くんですけれども、自称そういう特別栽培でやっているという農家でも、うちがお願いするのはその3分の1くらいです。その上で味に関しては、うちのバイヤーも当然チェックしますが、最終的にはお客さまの反応を見て決めていくというスタイルです。
Q:客の評判がよくて、その産品が売れた場合に、そのあとも取引を続ける、ということですね?
【高島】そうですね。野菜を扱っているような会社では、社長の舌がすべてを決めている、というところが多いのですが、うちはスタンスとして生産者側ではなくて消費者側に立っていますので、お客さまがいいというものがいい。基本的にすべての判断がそうです。だいたい3年くらいやってくると、良し悪しというのもわかってくるのですが。面白いなと思ったのは、インターネットで売ると、お客さまからの声というのがすごく多いんですよ。「先週のトマトの方が、やや美味しかった気がします」というようなメールが、ぶわーっと来ます。そうすると微妙な味の変化というのがすごくよくわかる。今度はそれを農家さんに対してフィードバックをしながら、食の宣伝をしているという感じです。
Q:生産物のチェックにはインターネットもメールも使えないと思うんですが、生産現場には、必ず足を運ばれるんですか?
【高島】うちの社員の誰かが、必ず行っています。ですからお客さんからのたくさんの声も、本当はメールで転送したいのですが、プリントアウトして、まとめてホッチキスで留めて持って行くんです。農家の方はそれを見ながら、最初はすごく怒る。「この客は全然わかっていない」とかいって、客のせいにしちゃうんです。でも何回も何回もそれをやると、「オイシックスの客はちょっと変わっているから、オイシックス用にちょっと栽培方法を変えてやろうか」というふうになってくる。今まで職人だったのが、すごくマーケティング的な視点を持ってくれるようになります。
Q:オイシックスから見て、農家とか、食品会社とか、今後食品を生産する人や会社には何が必要になってくると思いますか?
【高島】よく「安全・安心」といわれていますよね。とりあえず今は「安全・安心」を売りにしている部分はあるのですが、食べるものが安全であるということは、本来はわざわざアピールするようなことではないはずです。安全というのは前提でしかなくて、差別化にはなりえない。そうすると私たち自身もそうですし、生産者の方々も、安全を前提にどういう付加価値をつくり、どういう差別化をしていくのか、ということになると思うんです。たとえば給食に出てくるようなお惣菜よりも、レストランで出てくるようなお惣菜が家で食べられるようになっていくと思うんです。あるいはシニアの方々に評判がいいのは、普通の豆腐ではなくて、イソフラボンが強化されている豆腐だというようなことがある。そういう栄養効果による差別化もある。値段の差別化もあります。「安全・安心」というのはもう当たり前のこととして、そこから先の構想をいろいろ考えていきたいし、考えていただきたいです。
Q:生産者の人たちは、今のような説明で納得しますか?
【高島】ほとんどの生産者さんも流通業者さんも「安全・安心」が第一だと思い始めたという程度で、それが当たり前という感じではありません。そういう意味では主婦の方が求めているものとの間にはすごくギャップがあるかもしれないと感じています。食品流通業界というのは食べる人と作る人がすごく離れていて、情報も伝わりづらいんです。農家さんにもいろいろあって、今は農薬を使っている農家さんが圧倒的に多いのですが、そもそも農薬を使っているのを悪いことと思っていない農家さんも結構いる。じゃあなぜ農薬を減らすのかというと、スーパーでいわれるから、農協にいわれるからという感じなんです。
なかには自分の子どもが食べるものはまったく別の土地で作ったり、自分の子どもが農薬を使っている畑に入ると、「危ないから入っちゃだめ」と怒ったりする人もいる。もう消費者としては「そんなもん食わすなよ」と思うのですが、一方には本当は農薬を使いたくないという人もいるんですよ。でも農協しか売り先がないから、農薬を使わない、というのも怖い。脱農協は怖い、というのはすごく感じます。農薬を使う農家というのは、高い農業技術もないのですが、それは何年かやっていけば身につくことです。後は、売り先ですよね。お客さんにいいものを、できるだけ普通の値段で届けられる仕組みさえ作れれば、どんどん生産者も増えていくと思います。農家と消費者の間には、農協、流通、商社などが複雑に入っているためにこうなってしまったわけですが、両者の距離が近くなっていく方向にあるのは確かだと思います。
P.S.明日のための学習
13歳が20歳になるころには
-
いろいろな働き方の選択
-
IT[INformation Technology]
-
環境-21世紀のビッグビジネス
-
バイオは夢のビジネスか(commiong soon...)